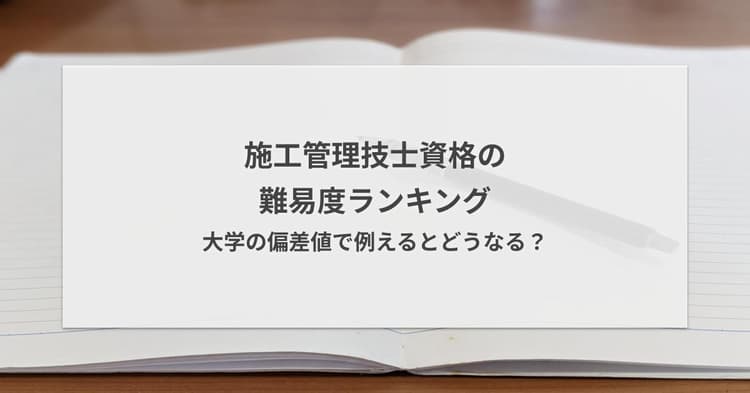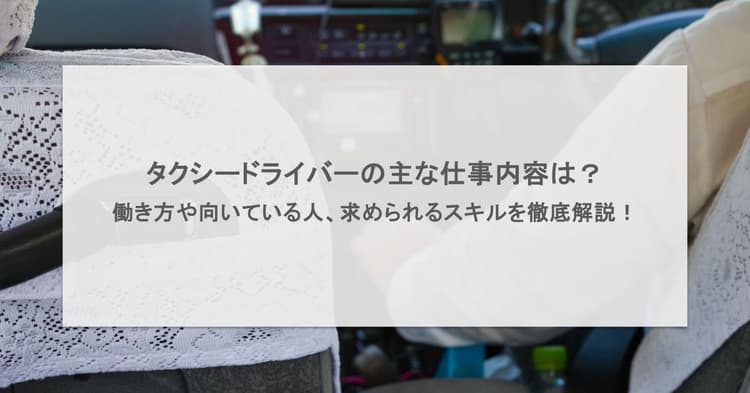1級管工事施工管理技士の難易度はやや高い!偏差値で例えると”54”
1級管工事施工管理技士は、建設系の国家資格であり、試験は決して簡単ではありません。
試験の難易度はやや高めで、偏差値で例えると”54”相当です。
※複数の大手資格スクールの発表情報をもとに独自で試算
合格者数は、毎年受験者の半数以下であり、実務経験者でも試験対策なしに合格はできません。
また第一次検定と第二次検定の試験があり、実質的に、短期間のストレート合格は難しいです。
ここからは1級管工事施工管理技士の過去5年間の合格率と、合格基準を詳しくみていきましょう。
1級管工事施工管理技士の令和6年度の合格率は39.9%・合格基準は60%以上
1級管工事施工管理技士の過去5年間の合格率は、18%~40%となっています。
年度 | ストレートの合格率(%)※1 | 第一次検定の合格率(%) | 第二次検定の合格率(%) |
|---|
令和6年度 | 39.9% | 52.3% | 76.2% |
|---|
令和5年度 | 23.3% | 37.5% | 62.1% |
|---|
令和4年度 | 24.5% | 42.9% | 57.0% |
|---|
令和3年度 | 17.6% | 24.0% | 73.3% |
|---|
令和2年度 | 21.4% | 35.0% | 61.0% |
|---|
※一般財団法人 全国建設研修センターのHP情報をもとに作成
※1. ストレート合格率:第一次検定の合格率×第二次検定の合格率
令和2年度から令和5年度までは、合格率が10%後半から20%前半でした。
一方で令和6年度は合格率が約40%まで伸びており、とくに第一次検定の合格率が上昇しました。
合格率が上昇した理由は、令和6年度から受験資格が緩和されたことがあると考えられています。
受験資格の緩和によって、1級管工事施工管理技士の第一次検定は19歳以上なら誰でも受験可能となり、大学などで学習を終えたばかりの大学生や若年層の受験者が増えたと推測できます。
なお1級管工事施工管理技士の合格基準は、第一次検定と第二次検定のいずれも60%以上です。
試験 | 合格基準 |
|---|
第一次検定(全体) | 得点が60%以上 |
|---|
第一次検定(施工管理法※応用能力) | 得点が50%以上 |
|---|
第二次検定 | 得点が60%以上 |
|---|
参照:令和7年度技術検定の合格基準について | 国土交通省
第一次検定で解答する問題は全体で60問となっており、36問以上の正解が必要です。
また施工管理法(応用能力)の問題数は8問なので、4問以上の正解が必要となります。
第二次検定では、合計4問(3問の必須問題と2問中1問の選択問題)の解答が必要です。
第二次検定には記述形式の解答もあり、部分点込みで60%以上の得点が必要となります。
部分的な足切り基準も設定されており、施工管理法(応用能力)が苦手な方は合格できません。
そのため適切な学習計画のもと、全体的にバランスよく学習を進めることがおすすめです。
\ 簡単30秒登録 /
> 管工事施工管理技士向けの求人をみてみる <
1級管工事施工管理技士と2級管工事施工管理技士の難易度・合格率の差は?
1級管工事施工管理技士は2級管工事施工管理技士より難易度が高く、資格試験で要求される知識の幅も経験の幅も広くなります。
過去5年間の合格率をみると、1級管工事施工管理技士が18%~40%です。
一方で、2級管工事施工管理技士の合格率は、22%~57%となっています。
資格の種類 | 年度 | ストレートの合格率(%) | 第一次検定の合格率(%) | 第二次検定の合格率(%) |
|---|
1級管工事施工管理技士 | 令和6年度 | 39.9% | 52.3% | 76.2% |
|---|
令和5年度 | 23.3% | 37.5% | 62.1% |
令和4年度 | 24.5% | 42.9% | 57.0% |
令和3年度 | 17.6% | 24.0% | 73.3% |
令和2年度 | 21.4% | 35.0% | 61.0% |
2級管工事施工管理技士 | 令和6年度 | 40.6% | 65.1% | 62.4% |
|---|
令和5年度 | 57.3% | 69.6% | 82.3% |
令和4年度 | 33.9% | 56.8% | 59.7% |
令和3年度 | 22.5% | 48.6% | 46.2% |
令和2年度 | 27.7% | 63.6% | 43.5% |
※一般財団法人 全国建設研修センターのHP情報をもとに作成
ご覧のとおり、1級管工事施工管理技士のほうが、合格率が低くなっています。
つづいては1級管工事施工管理技士と2級管工事施工管理技士の試験内容や担当できる工事の違いから、1級管工事施工管理技士の試験が難しくなる理由を見ていきましょう。
1級管工事施工管理技士と2級管工事施工管理技士で試験の内容や受験資格が違う
まず1級管工事施工管理技士と2級管工事施工管理技士では、第一次検定の問題数が変わります。
資格の種類 | 解答数 | 必要正答数 |
|---|
1級管工事施工管理技士 | 60問 | 36問 |
|---|
2級管工事施工管理技士 | 40問 | 24問 |
|---|
2つの試験ともに、合格基準は60%以上となっています。
そのため1級管工事施工管理技士の第一次検定は、36問以上。
2級管工事施工管理技士の第一次検定は、24問以上の正答数が求められます。
また試験の違いは解答数だけではなく、試験で問われる問題の質も大きく違います。
資格の種類 | 問題の質 |
|---|
1級管工事施工管理技士 | 応用問題中心 |
|---|
2級管工事施工管理技士 | 基本問題中心 |
|---|
1級管工事施工管理技士は、基本問題ではなく、応用問題が中心に問われます。
つまり1級管工事施工管理技士は、解答数が増えつつ、問題の質も難しくなるのです。
さらに1級管工事施工管理技士と2級管工事施工管理技士では、受験資格も異なります。
資格の種類 | 第一次検定の受験資格 | 第二次検定の受験資格 |
|---|
1級管工事施工管理技士 | 満19歳以上 | 1級第一次検定合格後 ・実務経験5年以上 ・特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 ・監理技術者補佐としての実務経験1年以上 2級第二次検定合格後 ・実務経験5年以上 ・特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 |
|---|
2級管工事施工管理技士 | 満17歳以上 | 2級第一次検定合格後 ・実務経験3年以上(建設機械種目については2年以上) 1級第一次検定合格後 ・実務経験1年以上 |
|---|
※一般財団法人 全国建設研修センターの公式HP情報をもとに作成
第一次検定の受験資格を比べると、1級管工事施工管理技士が満19歳以上で、2級管工事施工管理技士は満17歳以上となっており、2級は高校生でも受験できるとわかります。
第二次検定の受験資格では、1級管工事施工管理技士では、5年以上の実務経験が必須となっており、2級管工事施工管理技士は、必要な実務経験は3年以上です。
このように1級管工事施工管理技士は、年齢的にも経験的にも求められる要素が多くなります。
1級管工事施工管理技士と2級管工事施工管理技士で担当できる工事や役割が違う
1級管工事施工管理技士と2級管工事施工管理技士では、担当できる工事や役割が違います。
資格の種類 | 1級管工事施工管理技士 | 2級管工事施工管理技士 |
|---|
担当工事の規模 | 大規模 | 中小規模 |
|---|
監理技術者 | 可能 | 不可能 |
|---|
主任技術者 | 可能 | 可能 |
|---|
1級管工事施工管理技士になると、監理技術者として、大規模プラント工場や公共工事、商業施設などの現場責任者を担当できます。
■監理技術者とは
元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合に当該工事現場に配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のこと
引用:監理技術者について | 一般財団法人 建設業技術者センター
一方で2級管工事施工管理技士が担当できるのは、中小規模の現場における主任技術者までであり、監理技術者の役割を担当する事はできません。
主な工事としては、住宅や小規模ビルの配管工事など、比較的小規模な案件を中心に現場代理人として、現場監理を中心に任されることが多くなるでしょう。
1級管工事施工管理技士と2級管工事施工管理技士で年収が100万円以上も違う
1級管工事施工管理技士と2級管工事施工管理技士の差は、年収面でも大きくなります。
一般的に1級管工事施工管理技士を取得すると、資格手当と昇進・昇格によるベースアップがあり、年収ベースで100万円以上高くなることも多いです。
当社(プレックスジョブ)を活用して転職される方には、以下の年収レンジに収まることが多いです。
資格の種類 | 年収の目安 |
|---|
1級管工事施工管理技士 | 600万円~800万円 |
|---|
2級管工事施工管理技士 | 400万円~600万円 |
|---|
※プレックスジョブの転職実績(実務経験あり)をもとに算出
経験年数が同じ場合でも、1級管工事施工管理技士の資格保持者のほうが年収が高くなります。
専門性に見合った報酬を得るためにも、1級管工事施工管理技士の資格を取得したほうがよいでしょう。
ここまで紹介したとおり、1級管工事施工管理技士の試験は決して簡単ではありません。
偏差値でいうと”54”程度となっており、建設系の資格の中では、やや難しめな資格となっています。
実際に試験内容の専門性や記述式の問題があることから、「難しい...」と感じる受験者も多いです。
なお1級管工事施工管理技士と他の施工管理技士の難易度の差を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:施工管理技士資格の難易度ランキング
つづいては、1級管工事施工管理技士が難しいと言われる理由をみていきましょう。
1級管工事施工管理技士が難しいと言われる3つの理由
1級管工事施工管理技士が難しいと言われる理由は、以下の3つです。
- 1級管工事施工管理技士は試験の専門性が高いから
- 1級管工事施工管理技士には記述の解答があるから
- 1級管工事施工管理技士の受験に実務経験が必要だから
1級管工事施工管理技士は試験の専門性が高いから
1級管工事施工管理技士の試験は取り扱う内容が広範囲で、さらに問われる知識の専門性も高いです。
第一次検定では、管工事に関する機械設備全般の知識を問う問題が幅広く出題されます。
- 空調(空気調和、冷暖房、換気・排煙)
- 衛生(上下水道、ガス設備、浄化槽など)
- 設備・契約(機材、配管・ダクト、請負契約約款)
- 原論(環境工学、流体工学、熱工学など)
上記は、第一次検定で問われる内容の一部です。
いずれも高い専門知識が必要な領域で、環境工学や流体工学などの理論的な内容から給排水や空調などの実務的な設備知識まで幅広く問われます。
また管工事に関する専門知識だけではなく、施工管理や法律に関わる内容も問われます。
とくに施工管理法の分野では、ネットワーク工程表の計算問題や品質管理手法など、実務経験が乏しいと解くのが難しい応用問題も出題されます。
このように1級管工事施工管理技士の試験は、高い専門性を求められる問題が広範囲で出題されるので、難しいと言われているのです。
検定区分 | 検定科目 | 検定基準 |
|---|
第一次検定 | 機械工学等 | - 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な機械工学、衛生工学、電気工学、電気通信工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。
- 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の設備に関する一般的な知識を有すること。
- 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。
|
|---|
施工管理法 | - 監理技術者補佐として、管工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。
- 監理技術者補佐として、管工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。
|
法規 | - 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
|
第二次検定 | 施工管理法 | - 監理技術者として、管工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。
- 監理技術者として、設計図書で要求される設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。
|
|---|
引用:令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 | 一般財団法人 全国建設研修センター
1級管工事施工管理技士には記述の解答があるから
1級管工事施工管理技士の第二次検定は、与件に基づいた記述式の問題があります。
複数の選択肢から一つを選ぶテストとは違い、自分の言葉で答えを述べなければなりません。
そのため過去に出題された問題の暗記では対応できず、十分な現場経験と伝えられる文章力が必要です。
第二次検定には、記述式特有の対策が必要であり、「難しい...」と感じる人も多いです。
令和6年度の1級管工事施工管理技士の第二次検定では、以下の問題が出題されました。
鉄筋コンクリート造5階建ての事務所ビルの1階機械室に吸収冷温浄水器を設置し、屋上に冷却塔を設置する場合、次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。ただし、工程管理及び安全管理に関する事項は除く。
[設問1] 次の(1)~(4)に関する留意事項を、それぞれ解答欄の(1)~(4)に具体的かつ簡潔に記述しなさい。
- 吸収冷温水機の配置に関し、保守管理の観点からの留意事項
- 吸収冷温水機回りの配管施工に関し、保守管理の観点からの留意事項
- 冷却塔の基礎に関する留意事項
- 冷却塔回りの配管施工に関する留意事項
[設問2] 吸収冷温水機の特徴を解答欄の(1)に具体的かつ簡潔に記述しなさい。また、その機器に関して基礎への据え付け後から空調システム全体の総合試運転調整を始めるまでの期間の中で特に重要と考え実施する技術的事項を解答欄(2)に具体的かつ簡潔に記述しなさい。ただし、設問1に関する事項は除く。
引用:令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第二次検定 試験問題
上記の問題を解答するためには、施工プロセスを正確に理解して、現場経験をもとに具体的なエピソードや数値を挙げて説明する必要があります。
また正解が一つというわけではなく、論理が一貫した説得力のある文章を端的に書く能力も必要です。
このように自分の言葉で解答を求められるのも、1級管工事施工管理技士が難しいと言われる理由です。
1級管工事施工管理技士の受験に実務経験が必要だから
1級管工事施工管理技士の第二次検定は、受験資格として実務経験が必要です。
令和6年度の制度改正によって、第一次検定(旧:学科試験)は、満19歳以上であれば、実務経験不要で誰でも受験可能になりました。
一方で1級管工事施工管理技士の第二次検定は、第一次検定合格後に5年以上の実務経験(または特定の実務経験を含む3年以上)が必要となっており、試験のハードルは高いままの状態となっています。
つまり1級管工事施工管理技士を受験しているのは、基本的に実務経験が5年以上のベテランが多いです。
ベテランの施工管理技術者の受験者が多い中で、1級管工事施工管理技士の合格率は18%~40%なのです。
そもそも受験ハードルが高いことに加えて、その中でも合格率が低いので、「1級管工事施工管理技士は難しい」と言われるのです。
1級管工事施工管理技士は独学でも合格可能!必要な勉強時間は100時間~200時間
1級管工事施工管理技士は難しい試験ですが、独学でも十分に合格できる試験です。
なぜなら合格基準が全体の60%以上と明確であり、過去の試験問題と類似した問題の出題が多く、適切に教材を選んで計画的に学習をすれば、合格基準にも到達できるからです。
毎年、第一次検定の合格率は30%~50%で、第二次検定の合格率は50%~70%となっており、働きながら一発で合格する人も少なくありません。
とはいえ簡単な試験ではないので、一定の勉強時間は必要です。
一般的には、1級管工事施工管理技士の合格に、100時間~200時間の学習時間が必要と言われています。
ただしこの学習時間は、2級管工事施工管理技士合格者が前提となっており、未資格者だと、300時間~400時間の学習時間が必要になる場合が多いです。
総学習時間 | 1日1時間の場合 | 1日2時間の場合 |
100時間 | 100日 | 50日 |
|---|
200時間 | 200日 | 100日 |
|---|
300時間 | 300日 | 150日 |
|---|
400時間 | 400日 | 200日 |
|---|
1日2時間の学習時間を確保すれば、未資格者でも半年ほどで必要な学習時間を確保できます。
学習期間が長くなれば、学習した内容を忘れたり、面倒くさく感じることも増えるので、できるだけ短い期間で合格を目指すことをおすすめします。
1級管工事施工管理技士の第一次検定の対策は過去問題集5年分を繰り返す
1級管工事施工管理技士の第一次検定を独学で合格するには、過去問題集を徹底的に繰り返しましょう。
具体的には、直近5年(可能なら10年分)の過去問題集を3~4回繰り返し解いて、問題の出題パターンや出題傾向を把握することがおすすめです。
なぜなら過去の出題傾向を分析すると、第一次検定では、過去の試験で出題された問題と類似した問題が出るケースが多いからです。
実際に1級管工事施工管理技士の試験では、法令の条文や計算問題など、毎年同じテーマも多く、極端な奇問は少ない傾向にあります。
そのため過去10年分の問題と解答を繰り返し解けば、試験問題の8割以上は見たことがある論点になるといっても過言ではありません。
だからこそ独学で1級管工事施工管理技士の合格を目指すなら、過去問題集の反復が重要なのです。
1級管工事施工管理技士の第二次検定の対策は合格者に添削してもらう
1級管工事施工管理技士の第二次検定を独学で合格するには、記述問題を添削してもらってください。
というのも第二次検定の記述問題は、正解が一つではなく、自分自身では「どの程度の内容を書けば合格ラインになるか」の判断が難しいからです。
たとえば文字数の過不足や冗長な表現での記述、専門用語の使い方など、減点ポイントは多くあります。
これらを一人で気づくことは難しいですが、過去に合格したことのある先輩や講師に答案を見てもらい、添削を受けることで、合格レベルの解答に近づくことができます。
たとえば職場で1級管工事施工管理技士の資格を持っている上司や先輩に添削をしてもらったり、有料の添削サービスを使ったりする方法があります。
添削の際に、修正理由を聞いておけば、どの程度詳細に書けばよいのかの感覚も掴めます。
第二次検定の対策で大切なのは、自分の解答を客観的に評価してもらい、改善することです。
記述式の解答は個人的な目線になりやすいので、第三者の目線を入れることが合格への近道です。
ここまで紹介したとおり、1級管工事施工管理技士は取得が難しい資格ですが、学習時間を確保すれば、独学でも合格できる可能性が十分あります。
また1級管工事施工管理技士には、300時間以上の学習時間を使う以上に大きなメリットがあります。
つづいては1級管工事施工管理技士を取得するメリットと、資格取得後のキャリアパスをご紹介します。
1級管工事施工管理技士の資格を取得する3つのメリットとキャリアパス
1級管工事施工管理技士の資格を取得するメリットは、以下の3つです。
- 1級管工事施工管理技士の取得で年収が上がりやすくなる
- 1級管工事施工管理技士の資格保持者は転職で有利になる
- 1級管工事施工管理技士は安定した需要があり将来性も高い
1級管工事施工管理技士の取得で年収が上がりやすくなる
1級管工事施工管理技士を取得すると、資格手当や昇給・昇格による基本給のベースアップに加えて、ボーナスや賞与も増加する傾向があるため、年収が上がりやすくなります。
1級管工事施工管理技士の取得で年収が上がりやすい理由は、監理技術者(大規模工事の責任者)として現場の責任者を担当できるからです。
公共工事などの大規模工事の際には、建設業法で監理技術者の配置を義務付けられており、監理技術者を担当できる1級管工事施工管理技士がいないと、会社は工事を受注できません。
だからこそ会社側は、1級管工事施工管理技士を取得した社員の待遇をよくします。
関連記事:1級管工事施工管理技士の年収は?2級との違いや資格手当・将来性を解説
たとえば1級管工事施工管理技士を取得すると、毎月1万円~3万円の資格手当を受け取れる企業が多く、また役職が上がることで、年収が50万円以上アップするケースも多いです。
監理技術者には、責任者手当も出るので、合計で年収が100万円以上アップする方も珍しくありません。
とくに1級管工事施工管理技士を取得後、現場経験を積むことで、会社に必要不可欠な戦力となります。
だからこそ1級管工事施工管理技士を取得すると、年収が上がりやすくなるのです。
\ 簡単30秒登録 /
> 管工事施工管理技士の高年収求人をみてみる <
1級管工事施工管理技士の資格保持者は転職で有利になる
1級管工事施工管理技士の有資格者は、転職市場でも有利になります。
実際、1級管工事施工管理技士の資格は、スーパーゼネコンの応募条件にもなっていますし、中小規模の施工管理会社であれば、即戦力としてマネージャークラスでの採用もありえます。
たとえば大手設備会社で施工管理のポジションの場合、1級管工事施工管理技士の資格保持が必須条件とされたり、2級管工事施工管理技士の場合は20代に限定されていたりします。
なぜなら現在、大手企業では大規模プロジェクトを遂行するため、1級管工事施工管理技士の保持者を、一定以上確保する必要があり、2級管工事施工管理技士は将来性を込みでの採用となるからです。
なお先ほど紹介したとおり、1級管工事施工管理技士を取得すれば、年収の高いスーパーゼネコンや大手設備会社に転職できる可能性も十分あります。
大手企業に転職することで、仕事内容を維持したまま、年収1,000万円を超えることすら可能です。
このように1級管工事施工管理技士は、転職市場で大きな価値があります。
だからこそ早めに1級管工事施工管理技士を取得するのが、おすすめです。
なお管工事施工管理技士が転職するなら、プレックスジョブの利用をおすすめします。なぜならプレックスジョブは、書類選考の通過率を高めるために書類添削・書類作成の代行をしていたり、面接の通過率を高めるための面接対策(聞かれやすい質問や回答例の共有)をしたりして、転職の成功確率を最大限高めるサポートをしているからです。
プレックスジョブが施工管理の方にしているサポート内容については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:
施工管理の転職でプレックスジョブが選ばれている5つの理由
1級管工事施工管理技士は安定した需要があり将来性も高い
近年は公共インフラ設備の老朽化が進んでいるため、建設業界や施工管理に、安定した需要があります。
また都市の再開発や高層マンションなど、民間からの建設需要も強いです。
国土交通省の統計でも、過去15年で建設投資が42兆円から70兆円以上に増加していると示されており、建設投資は今後も増加する見込みがあります。
一方で建設業界は深刻な人手不足であり、さらに少子化・高齢化も進んでいます。
総務省の労働力調査(2025)によると、建設業界では29歳以下の若手が11.7%しかおらず、55歳以上の高齢者が36.7%と多くなっている状態です。
高齢化の傾向は年々加速しており、今後10年で多くの高齢者層が引退する見込みもあります。
このように施工管理の仕事は、需要が増加する一方で、供給側の施工管理技士が少なくなります。
スーパーゼネコンの鹿島建設では、定年前と同じ給与水準で、定年後に再雇用すると明記するほどです。
鹿島では、60歳で定年を迎える社員のうち、引き続き就労意欲を有する場合は再雇用制度を活用し、働き続けられるように制度と環境を整えており、再雇用率は約90%(再雇用希望者の再雇用率は100%)に達しています。 - 中略 - シニア社員が引き続き高いモチベーションを持って活躍できるよう、2024年度からは現場所長等の報酬については定年到達前と同水準を維持することにしました。
引用:鹿島 統合報告書 2024 | 鹿島建設株式会社
他にも大手ゼネコンを始めとして、多くの会社は、各社定年を延長したり、定年後再雇用制度を通して、60歳以上でも施工管理技士を雇っています。
他にも当社(プレックスジョブ)を利用した方には、70代で転職に成功した方もいます。
このように1級管工事施工管理技士を取得すると、仕事が安定したり将来性が高くなったりするだけではなく、定年後の仕事もある可能性が高いです。
将来的にも安定した収入を得たい人は、1級管工事施工管理技士を取得したほうがよいでしょう。
まとめ
本記事で紹介したとおり、1級管工事施工管理技士の難易度はやや高めで、偏差値で例えると”54”です。
本記事の重要なポイントをもう一度、ご紹介します。
- 令和6年度の合格率は39.9%
- 過去5年の合格率は18%~40%
- 試験の合格基準は60%以上(施工管理法で50%以上)
- 2級管工事施工管理技士の合格率は22%~57%
- 年収の目安は600万円~800万円
1級管工事施工管理技士の取得には、100時間~200時間※の学習が必要です。
※未資格の場合:300時間~400時間
ただし社内で昇進して年収を大幅にアップできたり、大手企業に転職できたりするチャンスがあるため、時間を投資する価値は十分ある資格と言えます。
資格を取得したあとは、価値を最大限活かすために、転職でキャリアアップを目指すのがおすすめです。
実際に当社(プレックスジョブ)には、1級管工事施工管理技士や2級管工事施工管理技士向けの求人を多数保有しており、あなたの市場価値を最大限活かした状態で転職をサポートします。
たとえば1級管工事施工管理技士なら年収800万円以上の求人がありますし、2級管工事施工管理技士には年収600万円近くの求人も紹介しています。
\ 簡単30秒登録 /
> 管工事施工管理技士の高年収求人をみてみる <
上記より低い年収で働いており、「もっと年収を上げていきたいな」という方は、ぜひ当社(プレックスジョブ)で求人を確認してください。
いまなら『年収診断』であなたの適正な年収を診断していますし、実際にどのような企業からどのような金額でオファーが来るかをお伝えすることも可能です。
→年収診断で適正な年収を確認する
1級管工事施工管理技士の難易度・偏差値に関するよくある質問
最後に1級管工事施工管理技士の難易度と偏差値に関するよくある質問をご紹介します。
【令和7年度】1級管工事施工管理技士の試験日・合格発表日はいつ?
令和7年度の1級管工事施工管理技士のスケジュールは、以下のとおりです。
受験申請区分 | 申請受付期間 | 試験日 | 合格発表 |
|---|
第一次検定 | インターネット受付期間 5月7日(水)~5月21日(水) 郵送締切日 5月23日(金)消印有効 | 9月7日(日) | 10月9日(木) |
|---|
第二次検定 | 同上 | 12月7日(日) | 令和8年3月4日(水) |
|---|
※インターネット申込はクレジットカード払い、コンビニ払いが選択できます。
コンビニ払い選択可能期間:令和7年5月7日(水)~令和7年5月18日(日)
クレジットカード払い選択可能期間:令和7年5月7日(水)~令和7年5月21日(水)
※コンビニ払いを選択した場合、支払締切日までにお支払いがないと申込が無効となり受検できませんのでご注意ください。
※申込は受検者本人が行ってください。
※申込受付期間を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受検申込できません。
引用:令和7年度 1級管工事施工管理技術検定の実施について | 一般財団法人 全国建設研修センター
1級管工事施工管理技士の試験は、年に一度しか受験できません。
つまり申請受付期間を過ぎると、1年間は受験できなくなるため、早めの申し込みがおすすめです。
1級管工事施工管理技士と2級管工事施工管理技士の難易度はどのくらい違う?
1級管工事施工管理技士は、2級管工事施工管理技士より難易度が高いです。
たとえば2級管工事施工管理技士の試験内容は基本問題が中心ですが、1級管工事施工管理技士の試験は応用問題を中心に問われます。
試験難易度の差は、合格率にも現れており、過去5年の1級管工事施工管理技士の合格率は18%~40%で、2級管工事施工管理技士の合格率は22%~57%となっています。
2つの試験で出題される問題は違うため、単純な比較はできませんが、1級管工事施工管理技士の試験が難しいことがわかるでしょう。
1級管工事施工管理技士と配管技能士の難易度はどのくらい違う?
1級管工事施工管理技士と配管技能士を比べると、1級管工事施工管理技士の難易度が高いと言われます。
なお1級管工事施工管理技士と配管技能士は、求められる要素が異なるため、単純な比較はできません。
ただし1級管工事施工管理技士は施工管理者向けの資格で、法規・施工計画・安全管理・品質管理などの監理面・マネジメント面の知識が問われたり、工事全体を見る能力を問われます。
一方で、配管技能士は現場作業者としての技能を試される資格です。
資格の種類 | 1級管工事施工管理技士 | 1級配管技能士 |
合格率(令和6年度) | 39.9% | 54.8% |
|---|
偏差値 | 54 | 52 |
|---|
学習時間 | 100時間~200時間 | 100時間~200時間 |
|---|
試験範囲 | | |
|---|
必要な能力 | | 現場作業者の技能 |
|---|
必要な学習時間は同じくらいですが、合格率は1級配管技能士のほうがやや高いです。
そのため1級管工事施工管理技士のほうが、少し難しいと考えておくとよいでしょう。
1級管工事施工管理技士と建築設備士の難易度はどのくらい違う?
1級管工事施工管理技士より建築設備士のほうが難しいと言われています。
なぜなら建築設備士の試験は、試験範囲が広く、合格率も低くなっているからです。
資格の種類 | 1級管工事施工管理技士 | 建築設備士 |
合格率(令和6年度) | 39.9% | 21.5% |
|---|
偏差値 | 54 | 58 |
|---|
学習時間 | 100時間~200時間 | 200時間~300時間 |
|---|
試験範囲 | | - 建築一般知識
- 建築法規
- 建築設備
- 建築設備基本計画
- 建設設備基本設計製図
|
|---|
必要な能力 | | |
|---|
建築設備士の試験は、1級管工事施工管理技士よりも学習時間が長く、合格率は低くなっています。
また1級管工事施工管理技士は管工事分野に特化した対策でOKですが、建築設備士は、建築物環境工学や電気工学、建築法規まで幅広く問われます。
とくに製図問題も難関であり、独学での学習は難しくなります。
だからこそ1級管工事施工管理技士より建築設備士のほうが難しいのです。
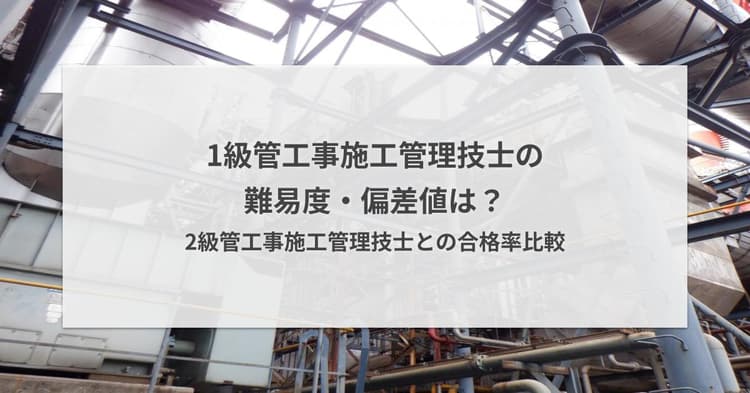







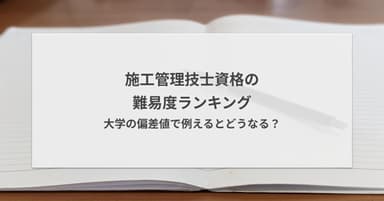

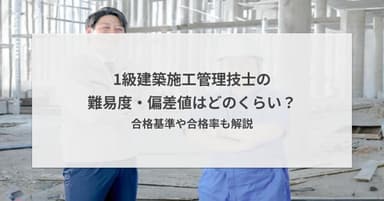
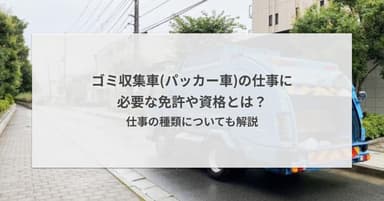
.jpg&w=384&q=75)