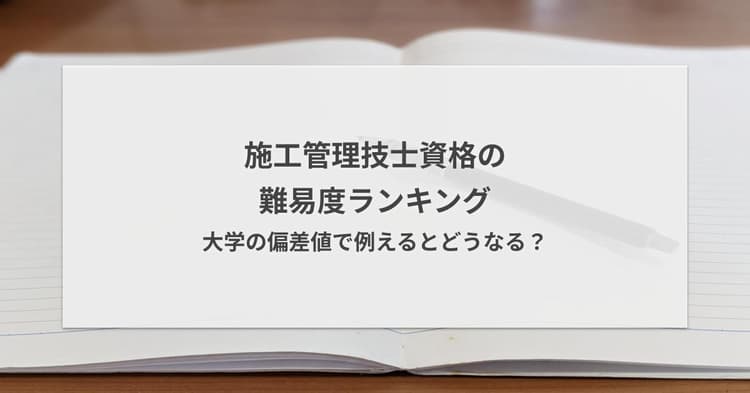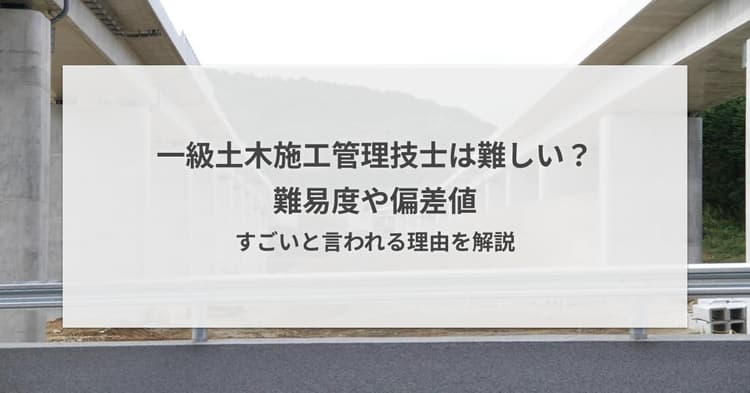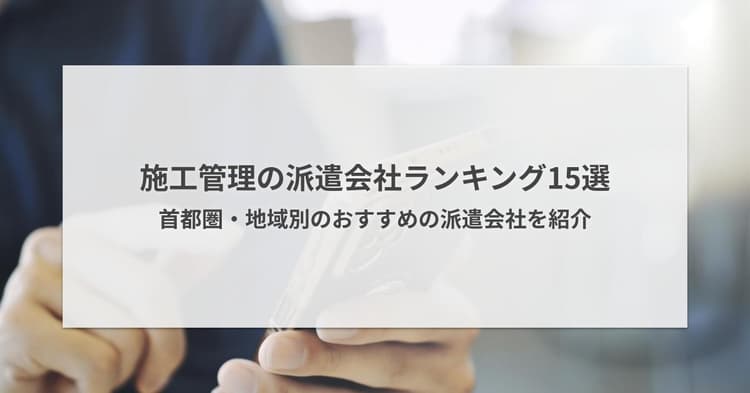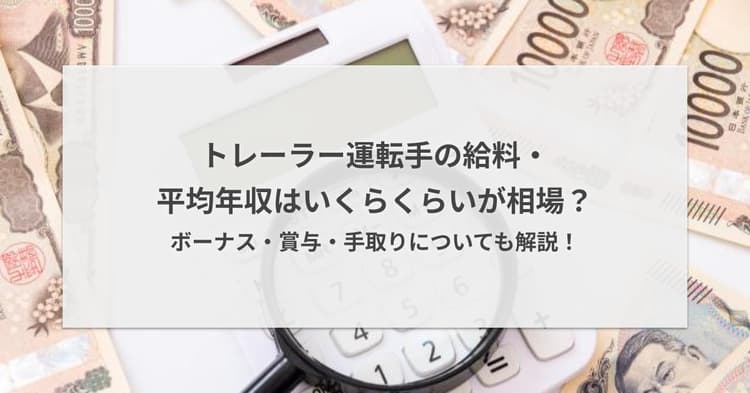1級電気工事施工管理技士の難易度は?偏差値換算でどのくらい難しい?
結論から言うと、1級電気工事施工管理技士の難易度は高めで、偏差値で言うと”54”※です。
※資格スクールなどの公開情報をもとに、弊社が独自で算出した参考値
偏差値は”50”が平均なので、1級電気工事施工管理技士の難易度は『やや高め』と言えます。
単純比較はできませんが、偏差値”54”の大学は、日本大学・東洋大学・龍谷大学・近畿大学・法政大学・関西学院大学などがあります。
つまり大学の偏差値レベルで言うと、日東駒専とGMARCHの中間くらいと考えておけばよいでしょう。
偏差値の高さからもわかるように、1級電気工事施工管理技士の難易度は、決して簡単ではありません。
なお1級電気工事施工管理技士だけではなく、施工管理技士は資格の取得難易度が高いです。1級電気工事施工管理技士を含めた、各資格の難易度を比較したい方は、以下の記事を参考にしてください。。
関連記事:
施工管理技士資格の難易度ランキング
つづいては、1級電気工事施工管理技士の過去6年の合格率推移を詳しく見ていきましょう。
1級電気工事施工管理技士の合格率は28.9%(令和7年度最新)
1級電気工事施工管理技士の過去6年の合格率は、以下のとおりです。
年度 | ストレートの合格率(%)※1 | 第一次検定の合格率(%) | 第二次検定の合格率(%) |
|---|
令和7年度 | 28.9% | 41.5% | 69.6% |
|---|
令和6年度 | 18.2% | 36.7% | 49.6% |
|---|
令和5年度 | 21.5% | 40.6% | 53.0% |
|---|
令和4年度 | 22.6% | 38.3% | 59.0% |
|---|
令和3年度 | 31.3% | 53.3% | 58.8% |
|---|
令和2年度 | 27.7% | 38.1% | 72.7% |
|---|
※一般財団法人 建設業振興基金のHP情報をもとに作成
※1. ストレート合格率:第一次検定の合格率×第二次検定の合格率
1級電気工事施工管理技士の合格率(過去6年間)は、18%~31%となっています。
なお1級電気工事施工管理技士は、第一次検定と第二次検定に分かれており、資格を取得するためには、2つの試験に通過する必要があります。
第一次検定の受験者数・合格者数・合格率の推移は、以下のとおりです。
第一次検定 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|
令和7年度 | 24,821人 | 10,290人 | 41.5% |
|---|
令和6年度 | 23,927人 | 8,784人 | 36.7% |
|---|
令和5年度 | 16,265人 | 6,606人 | 40.6% |
|---|
令和4年度 | 16,883人 | 6,458人 | 38.3% |
|---|
令和3年度 | 15,001人 | 7,993人 | 53.3% |
|---|
令和2年度 | 14,407人 | 5,493人 | 38.1% |
|---|
つづいて第二次検定の受験者数・合格者数・合格率の推移は、以下のとおりです。
第二次検定 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|
令和7年度 | 9,494人 | 6,607人 | 69.6% |
|---|
令和6年度 | 8,250人 | 4,093人 | 49.6% |
|---|
令和5年度 | 8,535人 | 4,527人 | 53.0% |
|---|
令和4年度 | 7,685人 | 4,537人 | 59.0% |
|---|
令和3年度 | 7,922人 | 4,655人 | 58.8% |
|---|
令和2年度 | 6,723人 | 4,887人 | 72.7% |
|---|
各試験の合格率が50%を超える年度もあるため、一見、簡単な試験に思えます。
ただし2つの試験の最終的な合格率は、30%以下の難関資格です。
なお第二次検定の受験は、第一次検定の合格が必須にも関わらず、令和6年度の合格率は50%以下です。
そのため1級電気工事施工管理技士の取得が簡単と考えているなら、認識を変えたほうがよいでしょう。
1級電気工事施工管理技士の合格基準・合格ラインは60%
1級電気工事施工管理技士の第一次検定は、合格基準が全体で得点が60%以上。
なおかつ施工管理法(応用能力)で、得点が50%以上です。
また第二次検定では、全体で得点が60%以上が基準となっています。
参照:令和7年度技術検定の合格基準について | 国土交通省
1級電気工事施工管理技士の第一次検定を受けるときに気をつけたいのは、全体で60%を超えていても、施工管理法(応用能力)の項目で50%を下回ると不合格になることです。
なお令和6年度の1級電気工事施工管理技士では、全体の必要解答数が60問となっており、施工管理法(応用能力)では6問となっています。
そのため全体で36問以上正解して、施工管理法で3問以上正解できれば合格となります。
1級電気工事施工管理技士の受験資格は19歳以上
1級電気工事施工管理技士は受験資格があり、誰でも受験できるわけではありません。
第一次検定と第二次検定について、それぞれの受験資格は、以下のとおりです。
試験 | 必要条件 |
|---|
第一次検定 | 試験実施年度に満19歳以上となる者 (令和7年度に申請する場合、生年月日が平成19年4月1日以前) |
|---|
第二次検定
(1級第一次検定合格者) | 1級電気工事第一次検定合格後、 ・実務経験5年以上 ・特定実務経験 (※1) 1年以上を含む実務経験3年以上 ・監理技術者補佐 (※2) としての実務経験1年以上 |
|---|
第二次検定
(1級第一次検定合格者・受験予定、および2級第二次検定合格者) | 2級電気工事第二次検定合格後、 ・実務経験5年以上 ・特定実務経験 (※1) 1年以上を含む実務経験3年以上 |
|---|
第二次検定
(1級第一次検定合格者・受験予定、および第一種電気工事士試験合格または免状交付者) | 2級電気工事第二次検定合格後、 ・実務経験5年以上 ・特定実務経験 (※1) 1年以上を含む実務経験3年以上 |
|---|
※1 建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円(建築一式工事については7,000万円)以上の建設工事であって、監理技術者・主任技術者(いずれも実務経験対象となる建設工事の種類に対応した監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者若しくは主任技術者として行った施工管理の実務経験を指します。
※2 1級電気工事施工管理技士補の資格を有し、かつ当該工事における主任技術者要件を充足する者が、監理技術者の専任が必要となる工事において、監理技術者の職務を専任として補佐した経験をいいます。単なる監理技術者の補助経験は対象になりません。
参照:令和7年度 1級 電気工事施工管理技術検定のご案内 | 一般財団法人 建設業振興基金
第一次検定の必要条件は、19歳以上という年齢制限のみですが、第二次検定の受験では最低で1年以上の実務経験が求められます。
1級電気工事施工管理技士の取得を目指す方は、資格取得と並行して実務経験を積んでいきましょう。
1級電気工事施工管理技士の試験内容
1級電気工事施工管理技士の第一次検定の検定科目は、以下のとおりです。
検定科目 | 検定基準 |
|---|
電気工学等 | - 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気工学、電気通信工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。
- 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等(以下「電気設備」という。)に関する一般的な知識を有すること。
- 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。
|
|---|
施工管理法 | - 監理技術者補佐として、電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。
- 監理技術者補佐として、電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。
|
|---|
法規 | - 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。
|
|---|
引用:検定基準の改正:1級電気施工管理 | 一般財団法人 施工管理技術検定
実際、令和6年度に出題された問題は、以下のようなものです。
[No.1] 5Ωの抵抗に100Vの電圧を一定時間加えたとき、この抵抗に6×10^5Jの熱量が発生した。加えた時間[分]として、適当なものはどれか。
- 5分
- 6分
- 21分
- 25分
[No.9] 電力系統における短絡容量の軽減対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 変電所の母線を分離する
- 送電線に限流リアクトルを設置する
- 直流連携により交流系統を分割する
- 低インピーダンスの変圧器を採用する
引用:令和6年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題 | 一般財団法人 施工管理技術検定
他にも『電気理論(計算)・系統/保護機器・設備・法規』などを中心に幅広い内容が問われます。
また1級電気工事施工管理技士の第二次検定の検定科目は、以下のとおりです。
検定科目 | 検定基準 |
|---|
施工管理法 | - 監理技術者として、電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。
- 監理技術者として、設計図書で要求される電気設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。
|
|---|
引用:検定基準の改正:1級電気施工管理 | 一般財団法人 施工管理技術検定
第二次検定で問われるのは、施工管理法のみとなります。
ただし第二次検定が難しいのは、経験記述の解答があることです。
実際に令和6年度に出題された問題では、以下のものがありました。
問題2. あなたの電気工事の経験を踏まえ、関連工事と輻輳する電気工事において、施工の計画から引き渡しまでの間の品質管理に関して、あなたがとくに留意すべき事項とその理由をあげなさい。その上で、それらに対して、あなたがとるべき対策を具体的に記述しなさい。ただし、解答は電気工事に付帯する工事を主体に記述しないこと。
引用:令和6年度 1級電気工事施工管理技術検定 第二次検定問題 | 一般財団法人 施工管理技術検定
上記のとおり、第二次検定は選択問題の他に記述式の解答があります。
なお記述式の解答には、単一の正解があるわけではありません。
あなた自身の経験をもとに解答する必要があるので、事前に経験の棚卸しをしておくことが大切です。
1級電気工事施工管理技士と2級電気工事施工管理技士の違いは?
1級電気工事施工管理技士と2級電気工事施工管理技士の試験は、試験の内容に大きな差はありません。
ただし2級電気工事施工管理技士が基本的な知識を問われる一方で、1級電気工事施工管理技士は、より専門的な知識や応用能力が問われます。
そのため試験の難易度を見ると、1級電気工事施工管理技士のほうが圧倒的に難しくなります。
1級電気工事施工管理技士の試験が難しい理由は、資格を取得した後に取り扱える工事規模や担当できる役割が変わるためです。
資格の種類 | 1級電気工事施工管理技士 | 2級電気工事施工管理技士 |
|---|
担当工事の規模 | 大規模 | 中小規模 |
|---|
監理技術者 | 可能 | 不可能 |
|---|
主任技術者 | 可能 | 可能 |
|---|
1級電気工事施工管理技士は、大規模工事での配置要件を満たせるため、監理技術者(現場の責任者)を担当できます。
一方で2級電気工事施工管理技士が担当できるのは、中小規模の工事の主任技術者までとなります。
だからこそ1級電気工事施工管理技士の資格試験は、2級電気工事施工管理技士よりも難しくなるのです。
なお1級電気工事施工管理技士と2級電気工事施工管理技士の過去5年の合格率は、以下のとおりでした。
資格の種類 | 年度 | ストレートの合格率(%) | 第一次検定の合格率(%) | 第二次検定の合格率(%) |
|---|
1級電気工事施工管理技士 | 令和7年度 | 28.9% | 41.5% | 69.6% |
|---|
令和6年度 | 18.2% | 36.7% | 49.6% |
令和5年度 | 21.5% | 40.6% | 53.0% |
令和4年度 | 22.6% | 38.3% | 59.0% |
令和3年度 | 31.3% | 53.3% | 58.8% |
令和2年度 | 27.7% | 38.1% | 72.7% |
2級電気工事施工管理技士 | 令和6年度 | 24.4% | 47.5% | 51.4% |
|---|
令和5年度 | 18.8% | 43.8% | 43.0% |
令和4年度 | 34.4% | 55.6% | 61.8% |
令和3年度 | 28.8% | 57.1% | 50.4% |
令和2年度 | 26.3% | 58.5% | 45.0% |
※一般財団法人 建設業振興基金のHP情報をもとに作成
\ 簡単30秒登録 /
> 電気工事施工管理技士向けの求人をみてみる <
1級電気工事施工管理技士の勉強方法は?独学でも合格できる!
1級電気工事施工管理技士は、独学でも十分合格できる可能性のある資格です。
実際に試験の難易度は高いですが、多くの受験者が仕事と両立しながら、受験して合格しています。
独学で合格するためのポイントは、適切な学習時間を確保して、テキスト選びを間違えないことです。
そこでつづいては、1級電気工事施工管理技士の資格を取得するために必要な学習時間やテキスト選びの方法などを解説します。
1級電気工事施工管理技士の学習時間は150時間~300時間が目安
複数の大手資格スクールの公式情報を見ると、1級電気工事施工管理技士の取得に必要な学習時間は、150時間~300時間※が一つの目安となっています。
※初学者の場合は、400時間~500時間が必要です。
300時間の学習時間を確保すると仮定した場合、1日の勉強時間は以下のとおりです。
学習期間 | 1日の勉強時間(分) |
|---|
1年 | 約50分 |
|---|
6ヶ月 | 約100分(1時間40分) |
|---|
3ヶ月 | 約200分(3時間20分) |
|---|
1級電気工事施工管理技士を3ヶ月で合格する学習時間は、1日3時間以上です。
施工管理の仕事は忙しいため、現実的に3時間以上を確保するのが難しい方もいるでしょう。
ただし学習期間が1年を超えると、モチベーションが下がって勉強が面倒になったり、学習内容を忘れたりする可能性もあります。
そのため可能な範囲で学習時間を確保し、短期間での1級電気工事施工管理技士の取得がおすすめです。
1級電気工事施工管理技士を独学での合格はテキスト選びが大切
1級電気工事施工管理技士を独学で合格を目指す場合は、スクールに通う以上にテキスト(教材)選びが重要になります。
なぜならテキストの内容や学習の進めやすさが、あなたの学習の進みやすさと直結するからです。
たとえば細かい情報まで記載されているテキストは安心感がある反面、情報量が多く、どこまで覚えればいいのかを判断できなくなりがちです。
逆に簡潔すぎるテキストでは、試験に出る知識が不足している可能性もあります。
そのため過去問題の出題範囲に沿って、必要事項が網羅されているテキストを選ぶのが理想です。
本屋に行くと、市販の参考書や資格学校のオリジナルテキストなど、数多くのテキストがあります。
実際に本屋で何冊かのテキストを手にとってみて、本文に記載されている解説を確認してみましょう。
その中で自分が理解しやすい解説のあるテキストを選べば、テキスト選びは間違いありません。
「そんなこと言われても、どれを選べばいいかわからない...」という方は、CICやTACなどの大手の資格スクールが提供しているテキストから一つを選べばOKです。
なおテキストを購入する際には、参考書だけではなく、必ず過去問題集もセットで購入してください。
参考書と過去問題集が連携しているテキストもあり、学習の観点からはセット商品が使いやすいです。
1級電気工事施工管理技士の第二次検定対策は上司・先輩に相談
1級電気工事施工管理技士の第二次検定を独学で突破するなら、上司・先輩に相談してください。
なぜなら第二次検定は、実務経験をもとにした記述式の解答が求められ、自分では解答が合っているのか間違っているのかを判断できにくいからです。
とくに独学で勉強していると、要点がずれていたり、採点基準を満たせなかったりします。
また試験委員が読みやすい構成になっていなかったり、論理が飛躍していたりするケースもあります。
一方で1級電気工事施工管理技士を取得している上司や先輩であれば、あなたの解答が合っているのか、それとも間違っているのかを判断できるでしょう。
自分の解答が合っているかを客観的に判断するためにも、1級電気工事施工管理技士の資格を持っている上司や先輩に相談するのがおすすめです。
なお相談できる上司や先輩がいない方は、資格学校や通信講座が提供する添削サービスを使いましょう。
3万円~5万円の費用がかかりますが、第二次検定の記述対策をサポートしてくれます。
1級電気工事施工管理技士の試験は、年に一度のみです。
一定の費用はかかりますが、一発合格で時間と労力をムダにしないための投資だと考えましょう。
ここまで紹介したとおり、1級電気工事施工管理技士は決して簡単な資格ではなく、150時間~300時間の勉強時間が必要になります。
しかし1級電気工事施工管理技士を取得するメリットは多く、1年間の学習時間を考慮しても、取得する価値のある資格です。
つづいては、1級電気工事施工管理技士を取得するメリットをみていきましょう。
1級電気工事施工管理技士の資格を取得するメリット
1級電気工事施工管理技士を取得するメリットは、以下の5つです。
- 1級電気工事施工管理技士は監理技術者を担当できる
- 1級電気工事施工管理技士は昇進・昇格に有利になる
- 1級電気工事施工管理技士は転職活動でも有利になる
- 1級電気工事施工管理技士の取得で年収がアップする
- 1級電気工事施工管理技士の取得で将来的に安定する
1級電気工事施工管理技士は監理技術者を担当できる
1級電気工事施工管理技士を取得すると、監理技術者として大規模工事の責任者を担当できることです。
■監理技術者とは
元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合に当該工事現場に配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のこと
引用:監理技術者について | 一般財団法人 建設業技術者センター
監理技術者は、一定規模以上の建設工事で現場に専任で配置が義務付けられる役割であり、1級の資格を持つ人だけが担当できます。
公共工事や大型商業施設の工事など、特定建設業の大規模工事には、必ず監理技術者が必要です。
どれだけ経験が豊富で実力のある方でも、1級の資格を持っていないと、監理技術者にはなれません。
実際の現場では、1級資格者のいる他社や他部署から人員を借りなければならないケースもあります。
つまり1級電気工事施工管理技士を取得すれば、自分自身が工事現場のトップ技術者となれるのです。
将来のキャリアを考えても、1級電気工事施工管理技士は有利なので、早めの取得をおすすめします。
1級電気工事施工管理技士は昇進・昇格に有利になる
1級電気工事施工管理技士の資格を持っていれば、社内で昇進・昇格するにも有利になります。
施工管理で働いていると、1級施工管理技士の資格取得が管理職などに昇格する条件の会社も多いです。
その理由はシンプルで、先ほど紹介したとおり、監理技術者として現場の責任者を担当できるからです。
監理技術者を担当できる1級施工管理技士の資格保持者がいれば、会社は大きな案件を受注できますし、結果として、売上や利益を伸ばせます。
逆に1級電気工事施工管理技士に辞められると、会社として大きな案件を受注できなくなります。
そのため1級電気工事施工管理技士の保持者を昇進・昇格させ、社内での待遇も改善するのです。
1級電気工事施工管理技士は転職活動でも有利になる
1級電気工事施工管理技士の資格は、転職活動においても有利になります。
そもそも建設業界は、慢性的な人手不足の状況で、転職市場は売り手市場です。
その中でも即戦力となる1級電気工事施工管理技士の保持者は、引く手あまたです。
とくに1級電気工事施工管理技士で経験も豊富の方だと、ゼネコンや設備工事会社、プラント企業などの幅広い会社から募集をかけられています。
なお年収600万円以上の求人だと、1級施工管理技士の保持が前提条件になっている会社も多いです。
逆に1級電気工事施工管理技士の資格を持っていれば、大手企業に転職できるチャンスもあります。
将来的なキャリアの幅を広げるためにも、早めの1級電気工事施工管理技士の取得をおすすめします。
なお電気工事施工管理技士が転職するなら、プレックスジョブの利用をおすすめします。なぜならプレックスジョブは、書類選考の通過率を高めるために書類添削・書類作成の代行をしていたり、面接の通過率を高めるための面接対策(聞かれやすい質問や回答例の共有)をしたりして、転職の成功確率を最大限高めるサポートをしているからです。
プレックスジョブが施工管理の方にしているサポート内容については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:
施工管理の転職でプレックスジョブが選ばれている5つの理由
1級電気工事施工管理技士の取得で年収がアップする
1級電気工事施工管理技士の取得は、直接的に年収を上げることが可能です。
たとえば多くの会社では、1級施工管理技士の資格手当として、月1万円~3万円が基本給に上乗せされるケースが多いですし、昇進・昇格で年収が50万円以上アップするケースもあります。
さらに1級電気工事施工管理技士を取得して、監理技術者を担当すれば、責任者手当も受け取れます。
そのため年収の合計が100万円以上アップするケースも少なくありません。
関連記事:1級電気工事施工管理技士の年収は高い?2級や電気工事士と年収を比較
社内で昇進するパターン以外にも、転職を通して、年収を上げる方法もあります。
1級電気工事施工管理技士の有資格者なら、地方でも年収600万円を超える求人はありますし、都内なら年収800万円を超える求人も一定数あります。
このように1級電気工事施工管理技士を取得すれば、年収を直接的にアップさせることが可能です。
\ 簡単30秒登録 /
> 電気工事施工管理技士の高年収求人をみる <
1級電気工事施工管理技士の取得で将来的に安定する
1級電気工事施工管理技士を取得すると、将来的にも安定して働くことが可能です。
というのも施工管理を含めた建設業界は人手不足であり、定年後も働く環境が整備されているからです。
大手ゼネコン企業も65歳以上の社員を再雇用したり、定年を延長したりして人手不足に対応しています。
鹿島では、60歳で定年を迎える社員のうち、引き続き就労意欲を有する場合は再雇用制度を活用し、働き続けられるように制度と環境を整えており、再雇用率は約90%(再雇用希望者の再雇用率は100%)に達しています。 - 中略 - シニア社員が引き続き高いモチベーションを持って活躍できるよう、2024年度からは現場所長等の報酬については定年到達前と同水準を維持することにしました。
引用:鹿島 統合報告書 2024 | 鹿島建設株式会社
今後もインフラ設備の老朽化などで、建設業界および施工管理に対する需要は増加する見込みです。
つまり人手不足の状況のなかで、施工管理技士に対する需要は年々増加しています。
だからこそ1級電気工事施工管理技士は、将来的にも安定するのです。
1級電気工事施工管理技士の難易度・偏差値を他の電気系資格と比較
電気関連の資格には、電気工事施工管理技士のほかにも、いくつかの資格があります。
偏差値 | 資格 |
|---|
66~ | 第一種 電気主任技術者 |
|---|
61~65 | 第二種 電気主任技術者 |
|---|
56~60 | 第三種 電気主任技術者 |
|---|
51~55 | - 1級電気工事施工管理技士
- 1級電気通信工事施工管理技士
- 第一種 電気工事士
|
|---|
~50 | - 2級電気工事施工管理技士
- 2級電気通信工事施工管理技士
- 第二種 電気工事士
|
|---|
つづいては各資格について、1級電気工事施工管理技士との比較をしていきます。
1級電気工事施工管理技士と1級電気通信工事施工管理技士の難易度を比較
1級電気工事施工管理技士と1級電気通信工事施工管理技士の難易度に、大きな差はありません。
2つの試験の最新(令和6年度)の合格率は、以下のとおりです。
資格の種類 | ストレートの合格率(%) | 第一次検定の合格率(%) | 第二次検定の合格率(%) |
|---|
1級電気工事施工管理技士 | 18.2% | 36.7% | 49.6% |
|---|
1級電気通信工事施工管理技士 | 16.6% | 40.5% | 40.9% |
|---|
※一般財団法人 建設業振興基金・一般財団法人 全国建設研修センターのHP情報をもとに作成
1級電気工事施工管理技士の合格率は、18.2%です。
一方で1級電気通信工事施工管理技士の合格率は、16.6%となっています。
試験の年度によって、合格率に多少の差はありますが、大きな差はありません。
ただし試験で問われる内容や担当できる業務領域が異なるので、試験を受ける際は注意が必要です。
1級電気工事施工管理技士と1級電気通信工事施工管理技士の試験内容は、それぞれ以下のとおりです。
資格の種類 | 検定科目 |
|---|
1級電気工事施工管理技士 | |
|---|
1級電気通信工事施工管理技士 | |
|---|
引用:
検定基準の改正:1級電気施工管理 | 一般財団法人 施工管理技術検定
1級電気通信工事施工管理技術検定 | 一般財団法人 全国建設研修センター
1級電気工事施工管理技士は、電気工学を中心とした試験です。
一方の1級電気通信工事施工管理技士は、電気通信工学が中心の試験です。
検定科目 | 扱う内容 |
|---|
電気工学 | 受変電設備や送配電設備など |
|---|
電気通信工学 | 電気通信設備、ネットワーク設備など |
|---|
2つの試験では試験内容や業務で取り扱う内容が異なるので、自分の業務や将来的なキャリアを考えて、受ける試験を選ぶことが重要になります。
1級電気工事施工管理技士と電気工事士(第一種・第二種)の難易度を比較
1級電気工事施工管理技士と第一種電気工事士は、試験の難易度が同じくらい。
第二種電気工事士は、1級電気工事施工管理技士より難易度が低めと言われています。
1級電気工事施工管理技士は、電気工事の施工管理(全体の監理・進行)をするための資格である一方、電気工事士は、実際に現場で作業を担当するための資格です。
そもそも担当領域が異なるため、一概に難易度を比較することはできないことに注意してください。
一般的に、1級電気工事施工管理技士と第一種電気工事士の難易度が同じくらいと考えておきましょう。
なお以下が1級電気工事施工管理技士と電気工事士について、令和6年度の試験の合格率となっています。
資格の種類 | 合格率(%)※1 |
|---|
1級電気工事施工管理技士 | 18.2% |
|---|
第一種 電気工事士 | 34.0% |
|---|
第二種 電気工事士 | 40.9% |
|---|
※一般財団法人 建設業振興基金・一般財団法人 電気技術者試験センターのHP情報をもとに作成
※1. 2つの試験をストレートで合格した場合の参考値
1級電気工事施工管理技士と電気主任技術者(電験一種・電験二種・電験三種)の難易度を比較
1級電気工事施工管理技士と電気主任技術者を比べると、電気主任技術者のほうが難しいと言われます。
電気主任技術者は、理論・電力・機械・法規の4科目からなる国家資格で、科目合格制度があるものの、最終的な合格率は、毎年10%前後と低くなっています。
とくに第一種電気主任技術者の難易度は高く、令和6年度のストレート合格率は4.6%でした。
資格の種類 | ストレートの合格率(%)※1 | 第一次検定/一次試験の合格率(%) | 第二次検定/二次試験の合格率(%) |
|---|
1級電気工事施工管理技士 | 18.2% | 36.7% | 49.6% |
|---|
第一種電気主任技術者 | 4.6% | 29.9% | 15.6% |
|---|
第二種電気主任技術者 | 5.7% | 28.9 % | 18.9% |
|---|
第三種電気主任技術者※2 | 16.4% | 16.4% | - |
|---|
※一般財団法人 建設業振興基金・一般財団法人 電気技術者試験センターのHP情報をもとに作成
※1. 2つの試験をストレートで合格した場合の参考値
※2. 第三種電気主任技術者は一次試験のみ
上記から分かるとおり、電気主任技術者の取得難易度は高いです。
とくに第一種電気主任技術者は、資格の取得難易度で言うと、一級建築士や日商簿記検定1級、中小企業診断士と同レベルとされています。
電気主任技術者は、取得に1,000時間以上(第一種:3,000時間以上)の勉強時間がかかるとされており、資格を取得するためには、かなり労力が必要です。
とはいえ第三種電気主任技術者であれば、資格取得は十分可能な範囲です。また電気主任技術者は転職先の幅広さも特徴で、ゼネコンやサブコンだけではなく、インフラ施設や再エネ関連企業への転職も可能になります。第三種電気主任技術者の転職先については、以下の記事で解説しているので参考にしてください。
関連記事:
電験三種のおすすめ転職先8選|大手に受かる5つの方法や求人情報を解説
まとめ
本記事で紹介したとおり、1級電気工事施工管理技士は取得難易度の高い資格です。
本記事の重要なポイントをもう一度、ご紹介します。
- 1級電気工事施工管理技士の合格率は18.2%
- 1級電気工事施工管理技士の偏差値は”54”
- 1級電気工事施工管理技士は独学でも合格可能
- 1級電気工事施工管理技士の取得で年収アップが可能
- 1級電気工事施工管理技士は他の資格と比較しても難しい
施工管理は人手不足の職種であり、1級電気工事施工管理技士は貴重な人材です。
そのため1級電気工事施工管理技士を取得すれば、転職市場では引く手あまたになるでしょう。
\ 簡単30秒登録 /
> 電気工事施工管理技士向けの求人をみてみる <
なお現時点で2級電気工事施工管理技士の方でも、転職で年収が600万円以上になる可能性もあります。
「自分の年収は適正なのかな?」と不安な方は、『年収診断』で自分の適正年収を調べてくださいね。
→自分の適正な年収を確認してみる
1級電気工事施工管理技士に関するよくある質問
最後に1級電気工事施工管理技士に関するよくある質問を紹介します。
1級電気工事施工管理技士を取得する前に転職してもよい?
1級電気工事施工管理技士を取得する前に転職しても問題ありません。
資格取得支援制度がある会社もあるので、転職後の1級電気工事施工管理技士取得も可能です。
ただし1級電気工事施工管理技士の取得後に転職したほうが、応募できる企業が増えることも事実です。
現状の職場や待遇を考えて、1級電気工事施工管理技士を取得する前に転職したほうがよいか、それとも資格の取得後に転職したほうがよいかを考えてください。
なおプレックスジョブで転職した方には、2級電気工事施工管理技士の資格で年収アップ転職を実現した方も多くいます。
現職で疲弊している方は、まずは転職で生活基盤や労働環境を整える方法もおすすめです。
→プレックスジョブで高待遇の求人をみてみる
いきなり1級電気工事施工管理技士から受験してもよい?
いきなり1級電気工事施工管理技士から受験しても、問題ありません。
1級電気工事施工管理技士の第一次検定は、満19歳以上であれば、誰でも受験可能です。
ただし1級電気工事施工管理技士の第一次検定合格後に、5年以上の実務経験※をしないと、第二次検定を受験することはできません。
※特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上、または監理技術者補佐としての実務経験1年以上
そのため最終的に1級電気工事施工管理技士の取得を目指す方は、まずは第一次検定の合格を目指して、その後は実務経験を積みながら、第二次検定の合格を目指す方法がおすすめです。
1級電気工事施工管理技士の合格発表(合否判定)はいつ?
令和7年度の1級電気工事施工管理技士のスケジュールは、以下のとおりです。
受験申請区分 | 申請受付期間 | 試験日 | 合格発表 |
|---|
第一次検定 | 2月14日(金)から 2月28日(金)まで 第一次検定のみの受験申請に限り 4月7日(月)まで(※1) | 7月13日(日) | 8月22日(金) |
|---|
第二次検定 | 同上(※2,3) | 10月19日(日) | 令和8年1月9日(金) |
|---|
※1 ネット申請のみ。インターネット環境がない方は、必ず2月28日までにご相談ください。
※2 願書販売は1月31日(金)からです。本財団WEBサイトからの注文は2月21日正午までとなっていますので、早めのご対応をお願いします。
※3 第一次検定の合格を確認してから、同年の第二次検定へ受検申請をすることはできません。
引用:令和7年度 1級 電気工事施工管理技術検定のご案内 | 一般財団法人 建設業振興基金
1級電気工事施工管理技士の試験は、一年に1度です。
そのため申請受付期限を過ぎると、試験を受験できるのは、1年後になります。
「申請受付期限を過ぎていた...」と失敗しないためにも、早めに受験申請の対応をしましょう。
1級電気工事施工管理技士の合格発表はどこで確認できる?
1級電気工事施工管理技士の合格発表は、運営元の一般財団法人 建設業振興基金のHPで確認できます。
令和7年度の試験では、第一次検定の合格発表日が『8月22日(金)』で、第二次検定の合格発表日が『令和8年1月9日(金)』となっています。
合格を確認する際は、受験番号の入力が必須なので、受験番号は忘れないように保管しておきましょう。








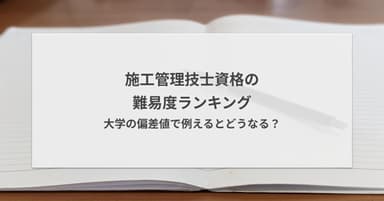
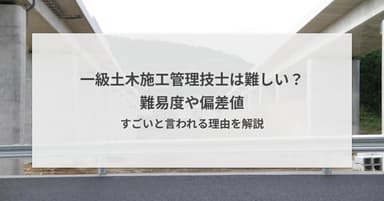
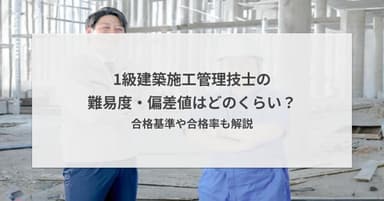
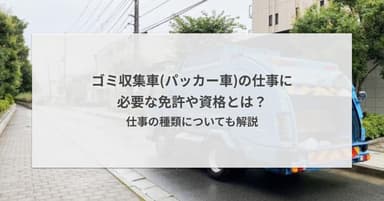
.jpg&w=384&q=75)