「実務経験も積んできたから、そろそろ施工管理技士の資格を取ろうかな」と考える際に、以下の不安を持っている方も多いのではないでしょうか?
「結局、私はどれを勉強すればいいの?」
「いきなり1級の資格を目指しても大丈夫?」
本記事では、最新の(令和6年度及び令和7年度)試験合格率をもとに施工管理技士の難易度ランキングや取得すべき資格。
あわせて施工管理技士を取得するメリットや、他資格との偏差値比較を解説します。
それでは施工管理技士資格の難易度ランキングから確認していきましょう。
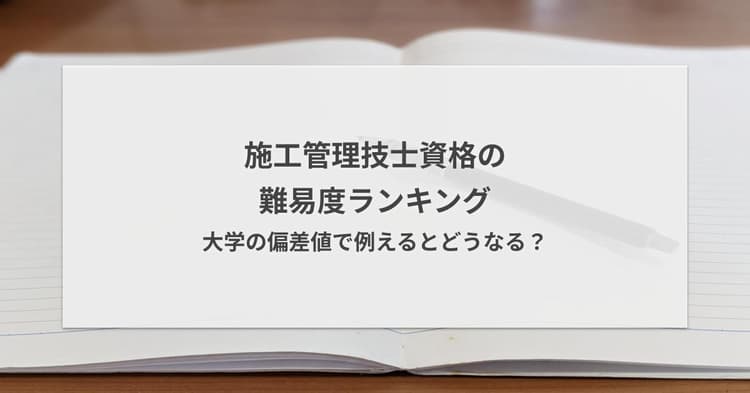
「実務経験も積んできたから、そろそろ施工管理技士の資格を取ろうかな」と考える際に、以下の不安を持っている方も多いのではないでしょうか?
「結局、私はどれを勉強すればいいの?」
「いきなり1級の資格を目指しても大丈夫?」
本記事では、最新の(令和6年度及び令和7年度)試験合格率をもとに施工管理技士の難易度ランキングや取得すべき資格。
あわせて施工管理技士を取得するメリットや、他資格との偏差値比較を解説します。
それでは施工管理技士資格の難易度ランキングから確認していきましょう。

施工管理技士は、建設業法で定められた国家資格であり、7つの種類があります。
1級施工管理技士の合格率を基準とした難易度ランキングは、以下のとおりです。
No | 資格の種類 | 合格率※1 |
|---|---|---|
1 | 1級建設機械施工管理技士 | 13.5% |
2 | 1級電気通信工事施工管理技士 | 16.6% |
3 | 1級造園工事施工管理技士 | 18.2% |
4 | 1級土木施工管理技士 | 18.3% |
5 | 1級建築施工管理技士 | 18.9% |
6 | 1級電気工事施工管理技士 | 28.9% |
7 | 1級管工事施工管理技士 | 39.9% |
※1. 試験実施団体の公表値(直近)をもとにストレート合格率※2を算出
※2. ストレート合格率:第一次検定の合格率×第二次検定の合格率
最も合格率が低い資格は、1級建設機械施工管理技士の13.5%です。
一方で、1級管工事施工管理技士の合格率は39.9%で最も高く、1級建設機械施工管理技士と比べると、20%以上高くなっています。
最も合格率が高い1級管工事施工管理技士でも、ストレートで合格できるのは、5人に2人(40%)以下。
半分以上はストレートで合格できないので、いずれの資格も難易度は高いと言えるでしょう。
なお2級施工管理技士の合格率を基準とした難易度ランキングは、以下のとおりとなっています。
No | 資格の種類 | 合格率※ |
|---|---|---|
1 | 2級土木施工管理技士 | 15.7% |
2 | 2級建築施工管理技士 | 19.6% |
3 | 2級建設機械施工管理技士 | 21.3% |
4 | 2級電気工事施工管理技士 | 24.4% |
5 | 2級造園工事施工管理技士 | 31.9% |
6 | 2級電気通信工事施工管理技士 | 36.5% |
7 | 2級管工事施工管理技士 | 40.6% |
※試験実施団体の公表値(直近)をもとにストレート合格率を算出
全体を通して、2級施工管理技士の合格率は、1級施工管理技士より高めです。
たとえば2級管工事施工管理技士は、直近の合格率が40%を超えています。
ただし2級土木施工管理技士の合格率は15.7%なので、簡単とは言えません。
それでは合格率の最も低い建設機械施工管理技士から、詳しく見ていきましょう。
施工管理技士で最も合格率(令和6年度・2024年度)が低いのは、1級建設機械施工管理技士で13.5%です。
なお過去5年の合格率の推移は、以下のとおりとなっています。
資格の種類 | 年度 | ストレートの合格率 | 第一次検定の合格率 | 第二次検定の合格率 |
|---|---|---|---|---|
1級建設機械施工管理技士 | 令和6年(2024年)度 | 13.5% | 27.8% | 48.4% |
令和5年(2023年)度 | 18.4% | 30.1% | 61.0% | |
令和4年(2022年)度 | 13.9% | 26.4% | 52.7% | |
令和3年(2021年)度 | 17.3% | 26.6% | 64.9% | |
令和2年(2020年)度 | 16.3% | 20.3% | 80.2% | |
2級建設機械施工管理技士 | 令和6年(2024年)度 | 21.3% | 41.2% | 51.8% |
令和5年(2023年)度 | 34.0% | 46.0% | 74.0% | |
令和4年(2022年)度 | 29.2% | 42.8% | 68.2% | |
令和3年(2021年)度 | 41.1% | 54.7% | 75.2% | |
令和2年(2020年)度 | 32.0% | 38.8% | 82.5% |
※一般社団法人 日本建設機械施工協会のHP情報等を参照
1級建設機械施工管理技士の合格率は、13%〜18%で推移しています。
2級建設機械施工管理技士の合格率は、20%~40%となっており、1級と比べると合格率は高めです。
1級建設機械施工管理技士の第一次検定は、土木工学の知識に加えて、建設機械原動機や石油燃料、建設機械などの専門知識が問われます。
また第二次検定では、組み合わせ施工管理・施工管理法・建設機械施工管理の3項目で記述式での回答を求められます。
これらのことが、1級建設機械施工管理技士の難易度を高めている要因でしょう。
なお1級建設機械施工管理技士と2級建設機械施工管理技士では、担当できる工事や役割が変わります。
資格名 | 1級建設機械施工管理技士 | 2級建設機械施工管理技士 |
担当工事の規模 | 大規模 | 中小規模 |
|---|---|---|
監理技術者 | 可能 | 不可能 |
主任技術者 | 可能 | 可能 |
1級建設機械施工管理技士と2級建設機械施工管理技士の大きな違いは、担当工事の規模と監理技術者を担当できるかです。
1級建設機械施工管理技士を取得すると、下請けの業者を使う『特定建設業の工事』を担当できるため、工事規模が大きくなりやすいです。
たとえば1級建設機械施工管理技士では、重機を使った大規模な道路の地盤改良や掘削・整地などの公共工事を担当することが多くなるでしょう。
1級電気通信工事施工管理技士の合格率(令和6年度・2024年度)は16.6%で、施工管理技士で二番目に低いです。
過去5年の電気通信工事施工管理技士の合格率推移は、以下のとおりです。
資格の種類 | 年度 | ストレートの合格率 | 第一次検定の合格率 | 第二次検定の合格率 |
|---|---|---|---|---|
1級電気通信工事機械施工管理技士 | 令和6年(2024年)度 | 16.6% | 40.5% | 40.9% |
令和5年(2023年)度 | 18.9% | 51.2% | 37.0% | |
令和4年(2022年)度 | 20.4% | 54.5% | 37.4% | |
令和3年(2021年)度 | 17.6% | 58.6% | 30.1% | |
令和2年(2020年)度 | 24.2% | 49.1% | 49.3% | |
2級電気通信工事施工管理技士 | 令和6年(2024年)度 | 36.5% | 68.6% | 53.2% |
令和5年(2023年)度 | 21.7% | 59.9% | 36.3% | |
令和4年(2022年)度 | 21.0% | 59.1% | 35.6% | |
令和3年(2021年)度 | 21.2% | 70.4% | 30.1% | |
令和2年(2020年)度 | 22.5% | 66.4% | 33.9% |
※一般財団法人 全国建設研修センターのHP情報等を参照
1級電気通信工事施工管理技士の合格率は、16%~24%です。
2級電気通信工事施工管理技士の合格率は21%~36%で、1級電気通信工事施工管理技士より高いです。
電気通信工事施工管理技士の試験は、電気通信工学や電気工学に加えて、土木工学などの建築学に関する一般的な知識が問われます。
それだけではなく、有線・無線電気通信設備や放送機械設備などの専門知識も問われます。
だからこそ電気通信工事施工管理技士は合格率20%未満と、低い数字になっているのです。
なお電気通信工事施工管理技士になると、インターネットや回線を扱う工事がメインとなります。
将来的に成長する可能性が高い分野なので、1級電気通信工事施工管理技士の価値は十分高いでしょう。
次に合格率が高いのは、1級造園工事施工管理技士の18.2%となっています。
過去5年間の合格率推移は、以下のとおりです。
資格の種類 | 年度 | ストレートの合格率 | 第一次検定の合格率 | 第二次検定の合格率 |
|---|---|---|---|---|
1級造園工事施工管理技士 | 令和6年(2024年)度 | 18.2% | 45.4% | 40.0% |
令和5年(2023年)度 | 15.2% | 35.2% | 43.3% | |
令和4年(2022年)度 | 20.2% | 44.0% | 46.0% | |
令和3年(2021年)度 | 14.4% | 35.9% | 40.0% | |
令和2年(2020年)度 | 16.2% | 39.6% | 41.0% | |
2級造園施工管理技士 | 令和6年(2024年)度 | 31.9% | 51.1% | 62.4% |
令和5年(2023年)度 | 27.0% | 51.5% | 52.4% | |
令和4年(2022年)度 | 23.0% | 56.7% | 40.6% | |
令和3年(2021年)度 | 21.2% | 49.8% | 42.6% | |
令和2年(2020年)度 | 25.1% | 58.3% | 43.0% |
※一般財団法人 全国建設研修センターのHP情報等を参照
1級造園工事施工管理技士の合格率は、15%~20%です。
また2級造園工事施工管理技士は、20%~30%の合格率となっています。
造園工事施工管理技士は、他の施工管理技士と比べても、専門性が強い資格です。
項目 | 造園工事施工管理技士 |
仕事内容 |
|
|---|---|
試験範囲 |
|
たとえば造園原論では、造園史という歴史も問われることになります。
また専門性が高い分、扱う仕事内容も限定的なものになりやすいです。
その分、公園や緑地などの工事を担当したいという方には、1級造園工事施工管理技士がおすすめです。
施工管理技士で四番目に合格率が低いのが、1級土木施工管理技士の18.3%です。
土木施工管理技士の過去5年の合格率の推移は、以下のとおりとなっています。
資格の種類 | 年度 | ストレートの合格率 | 第一次検定の合格率 | 第二次検定の合格率 |
|---|---|---|---|---|
1級土木施工管理技士 | 令和6年(2024年)度 | 18.3% | 44.4% | 41.2% |
令和5年(2023年)度 | 16.4% | 49.5% | 33.2% | |
令和4年(2022年)度 | 15.7% | 54.6% | 28.7% | |
令和3年(2021年)度 | 22.2% | 60.6% | 36.6% | |
令和2年(2020年)度 | 18.6% | 60.1% | 31.0% | |
2級土木施工管理技士 | 令和6年(2024年)度 | 15.7% | 44.6% | 35.3% |
令和5年(2023年)度 | 32.8% | 52.1% | 62.9% | |
令和4年(2022年)度 | 24.3% | 64.0% | 37.9% | |
令和3年(2021年)度 | 26.3% | 73.6% | 35.7% | |
令和2年(2020年)度 | 30.6% | 72.6% | 42.2% |
※一般財団法人 全国建設研修センターのHP情報等を参照
1級土木施工管理技士の合格率は、15%~22%です。
一方で2級土木施工管理技士の合格率は、15%~33%となっています。
土木施工管理技士は、比較的、合格率が高めな試験ですが、資格の取得は決して簡単ではありません。
建築施工管理技士と並んで、社会のインフラを作る仕事ですし、ダムやトンネルなどの大規模公共工事を扱うことも多いです。
第一次検定では、土木工学に関する一般的な知識や施工管理に関する知識や法律が問われます。
また第二次検定では、経験記述による現場での応用力が試される問題もあります。
ただし土木施工管理技士は需要が強く、受験者数も多いため、資格スクールや独学用の教材も豊富です。
そのため難易度と比べても、勉強自体は進めやすい状況となっており、独学でも合格可能性はあります。
1級土木施工管理技士を取得すれば、年収1,000万円の可能性もあるので、早めの取得をおすすめします。
1級建築施工管理技士の合格率(令和7年度・2025年度)は18.9%でした。
過去5年間の合格率の推移は、以下のとおりとなっています。
資格の種類 | 年度 | ストレートの合格率 | 第一次検定の合格率 | 第二次検定の合格率 |
|---|---|---|---|---|
1級建築施工管理技士 | 令和7年(2025年)度 | 18.9% | 48.5% | 39.0% |
令和6年(2024年)度 | 14.8% | 36.2% | 40.8% | |
令和5年(2023年)度 | 18.9% | 41.6% | 45.5% | |
令和4年(2022年)度 | 21.2% | 46.8% | 45.2% | |
令和3年(2021年)度 | 18.9% | 36.0% | 52.4% | |
令和2年(2020年)度 | 20.8% | 51.1% | 40.7% | |
2級建築施工管理技士 | 令和6年(2024年)度 | 19.6% | 48.2% | 40.7% |
令和5年(2023年)度 | 12.1% | 37.7% | 32.0% | |
令和4年(2022年)度 | 26.9% | 50.7% | 53.1% | |
令和3年(2021年)度 | 20.0% | 37.9% | 52.9% | |
令和2年(2020年)度 | 9.9% | 35.0% | 28.2% |
※一般財団法人 建設業振興基金のHP情報等を参照
1級建築施工管理技士の合格率は、15%~20%です。
また2級建築施工管理技士の合格率は、10%~27%となっています。
2級建築施工管理技士の合格率が低いので、難易度が高く感じますが、1級建築施工管理技士は試験範囲が広く、専門性も深くなるため、難易度が高くなります。
関連記事:1級建築施工管理技士の難易度・偏差値は?
なお1級建築施工管理技士と2級建築施工管理技士では、扱う工事の規模や役割が変わります。
項目 | 1級建築施工管理技士 | 2級建築施工管理技士 |
担当する工事 |
|
|
|---|---|---|
監理技術者 | 可能 | 不可能 |
主任技術者 | 可能 | 可能 |
1級建築施工管理技士になると、担当するプロジェクトの規模は大きく、複雑になります。
所属する企業によっては、予算数百億円から数千億円のプロジェクトを担当することもあります。
このようなプロジェクトを担当するには、高い専門性が必要になるため、1級建築施工管理技士の資格は難しくなるのです。
\ 簡単30秒 /
> 建築施工管理技士の求人情報をみてみる <
1級電気工事施工管理技士の合格率(令和7年度・2025年度)は28.9%でした。
過去5年の電気工事施工管理技士の合格率推移は、以下のとおりです。
資格の種類 | 年度 | ストレートの合格率 | 第一次検定の合格率 | 第二次検定の合格率 |
|---|---|---|---|---|
1級電気工事施工管理技士 | 令和7年(2025年)度 | 28.9% | 41.5% | 69.6% |
令和6年(2024年)度 | 18.2% | 36.7% | 49.6% | |
令和5年(2023年)度 | 21.5% | 40.6% | 53.0% | |
令和4年(2022年)度 | 22.6% | 38.3% | 59.0% | |
令和3年(2021年)度 | 31.3% | 53.3% | 58.8% | |
令和2年(2020年)度 | 27.7% | 38.1% | 72.7% | |
2級電気工事施工管理技士 | 令和6年(2024年)度 | 24.4% | 47.5% | 51.4% |
令和5年(2023年)度 | 18.8% | 43.8% | 43.0% | |
令和4年(2022年)度 | 34.4% | 55.6% | 61.8% | |
令和3年(2021年)度 | 28.8% | 57.1% | 50.4% | |
令和2年(2020年)度 | 26.3% | 58.5% | 45.0% |
※一般財団法人 建設業振興基金のHP情報等を参照
1級電気工事施工管理技士の合格率は、18%~31%となっています。
2級電気工事施工管理技士の合格率は18%~34%で、1級電気工事施工管理技士と同じ水準です。
とはいえ1級電気工事施工管理技士のほうが、より深い専門性を問われるため難しいです。
たとえば第一次検定では、電気工学の全般的な知識に加えて、機械設備や発電設備、制御装置などの専門知識が問われます。
また第二次検定では、施工経験の記述問題や電気設備全般の用語・語句説明も求められます。
このように幅広く、深い専門性が求められるため、電気工事施工管理技士は難しいのです。
関連記事:1級電気工事施工管理技士の難易度は?
なお1級電気工事施工管理技士の有資格者は、電力・電気設備会社から引く手あまたの状態です。
以下にあるような安定したインフラ会社に転職したい方は、ぜひ1級電気工事施工管理技士の取得を目指してください。
\ 簡単30秒 /
> 電気工事施工管理技士の求人情報をみてみる <
施工管理技士で最も合格率(令和6年度・2024年度)が高いのは、1級管工事施工管理技士の39.9%です。
管工事施工管理技士の過去5年の合格率推移は、以下のとおりです。
資格の種類 | 年度 | ストレートの合格率 | 第一次検定の合格率 | 第二次検定の合格率 |
|---|---|---|---|---|
1級管工事施工管理技士 | 令和6年(2024年)度 | 39.9% | 52.3% | 76.2% |
令和5年(2023年)度 | 23.3% | 37.5% | 62.1% | |
令和4年(2022年)度 | 24.5% | 42.9% | 57.0% | |
令和3年(2021年)度 | 17.6% | 24.0% | 73.3% | |
令和2年(2020年)度 | 21.4% | 35.0% | 61.0% | |
2級管工事施工管理技士 | 令和6年(2024年)度 | 40.6% | 65.1% | 62.4% |
令和5年(2023年)度 | 57.3% | 69.6% | 82.3% | |
令和4年(2022年)度 | 33.9% | 56.8% | 59.7% | |
令和3年(2021年)度 | 22.5% | 48.6% | 46.2% | |
令和2年(2020年)度 | 27.7% | 63.6% | 43.5% |
※一般財団法人 全国建設研修センターのHP情報等を参照
1級管工事施工管理技士の合格率は、18%~40%です。
また2級管工事施工管理技士の合格率は、22%~57%となっています。
1級管工事施工管理技士は、令和6年(2024年)度の合格率が高く、難易度が低いと思ってしまうかもしれません。
ただし令和6年(2024年)度以外の合格率は20%前後となっており、決して簡単な資格ではありません。
関連記事:1級管工事施工管理技士の難易度・偏差値
管工事施工管理技士は、空調設備やガス配管設備、上下水道配管設備などの配管工事を担当します。
そのため試験でも、環境工学や熱工学に加えて、空調や衛生などの専門性が高い内容も問われます。
なお求人を見ても、住宅系ハウスメーカーから大型プラント工場・ゼネコンまで幅広く需要があります。
将来的にも需要の減らない分野なので、コスパをよく1級施工管理技士を取りたい方にはおすすめです。
\ 簡単30秒 /
> 管工事施工管理技士の求人情報をみてみる <
施工管理技士の難易度を偏差値で表すと、1級施工管理技士が52~55、2級施工管理技士が48~50ほどだとされています。※複数の資格サイトを参照
イメージしやすいように、施工管理技士などの資格難易度を、大学の偏差値で例えてみました。
偏差値※ | 資格 | 大学 |
|---|---|---|
66~ | 一級建築士・技術士・弁理士・医師・公認会計士など | 東京大学・京都大学・慶應義塾大学・早稲田大学など |
61~65 | 原子炉主任技術者・第二種 電気主任技術者 ・行政書士など | 神戸大学・横浜国立大学・上智大学・大阪大学など |
56~60 | 管理業務主任者・二級建築士・測量士・宅建など | 明治学院大学・中央大学・同志社大学・関西大学など |
51~55 | 1級施工管理技士・1級とび技能士・浄化槽管理士など | 順天堂大学・近畿大学・専修大学・東洋大学など |
46~50 | 2級施工管理技士・液化石油ガス設備士・消防設備士 甲種など | 創価大学・拓殖大学・大東文化大学・東京工科大学など |
※複数サイトや資格スクールの公開情報をもとに、弊社が独自で算出した参考値です。難易度評価は、一次/二次の公表合格率を主指標としています。
大学の偏差値で例えると、1級施工管理技士は日本大学や東洋大学と同じくらい。
2級施工管理技士は、創価大学や拓殖大学を同じくらいの難易度と考えるとよいでしょう。
もちろん大学受験と資格試験を並列に語ることはできませんが、大学進学率が60%を下回っていることを考えると、施工管理技士の取得が簡単ではないことがわかります。
「7種類あるのはわかるけど、結局どれを取得すればいいの?」と迷っている方は、自分の専門領域や、今後チャレンジしたい領域の資格を取得してください。
資格ごとの担当工事の領域は、以下のとおりです。
資格の種類 | 担当工事の領域 |
|---|---|
土木施工管理技士 | 河川、道路、海岸、ダム、港湾、鉄道、空港、上下水道、橋梁、トンネル、土木構造物解体、コンクリート基礎など |
建築施工管理技士 | 住宅、商業施設、学校、病院、オフィスビル、工場、倉庫、建築物解体工事など |
管工事施工管理技士 | 空調設備、給排水衛生設備、ガス配管、空調・換気ダクト、消防用配管、浄化槽設備など |
電気工事施工管理技士 | 発電所・変電所、発電・変電設備、送配電線、建物の電気配線、信号機・街路灯など |
電気通信工事施工管理技士 | 通信線路、アンテナ、放送装置、ネットワーク設備、半導体工場など |
建設機械施工管理技士 | 建設機械を用いた掘削・整地・締固め工事、しゅんせつ、道路舗装など |
造園施工管理技士 | 庭園、公園、緑地、植栽、地被、園路・広場、あずまや・ベンチ等の公園施設など |
河川や道路関連の公共工事を仕事にする方は土木施工管理技士がおすすめですし、通信設備関連の仕事にチャレンジしたい方は電気通信工事施工管理技士がおすすめになります。
なおすでに、いずれかの施工管理技士を取得している方は、ダブルライセンスとして、二つ目の施工管理技士資格を目指すこともおすすめです。
対応できる仕事の幅が広がるので、収入がアップしたり、より大きな規模の仕事に携われたりします。
関連記事:
施工管理技士の平均年収は641万円|業界別ランキングと1000万目指す方法
施工管理技士の資格一覧!資格を取得するメリット
施工管理技士の受験資格は、『1級施工管理技士・2級施工管理技士』と『第一次検定・第二次検定』でそれぞれ異なります。
つづいては1級施工管理技士と2級施工管理技士の受験資格を見ていきましょう。
1級施工管理技士の受験資格は、以下のとおりです。
試験 | 必要条件 |
|---|---|
1次試験 | 試験実施年度に満19歳以上となる者 (令和7年度に申請する場合、生年月日が平成19年4月1日以前) |
2次試験 | 1級第一次検定合格後 ・実務経験5年以上 ・特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 ・監理技術者補佐としての実務経験1年以上 |
2次試験 | 2級第二次検定合格後 ・実務経験5年以上 ・特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 |
※令和5年11月に、施工管理技士の受験資格は変更されています
2級施工管理技士の受験資格は、以下のとおりです。
試験 | 必要条件 |
|---|---|
1次試験 | 試験実施年度に満19歳以上となる者 (令和7年度に申請する場合、生年月日が平成19年4月1日以前) |
2次試験 | 2級第一次検定合格後 ・実務経験3年以上 (建設機械種目については2年以上) |
2次試験 | 1級第一次検定合格後 ・実務経験1年以上 |
※令和5年11月に、施工管理技士の受験資格は変更されています
ここまで紹介しているとおり、施工管理技士の取得は決して簡単ではなく、受験資格の条件もあります。
ただし施工管理を仕事にする人は年収が上がったり、キャリアアップできたりする可能性が高まるため、施工管理技士の資格を取得するメリットは大きいです。
\ 簡単30秒 /
> 施工管理技士向けの非公開求人をみてみる <
そこでつづいては、施工管理技士を取得するメリットを紹介していきます。
施工管理技士資格を取得するメリットは、以下の5つがあります。
施工管理技士を取得すれば、現職で昇進・昇格して年収が上がる可能性があります。
多くの会社では、主任や課長などに昇格する条件として、施工管理技士の取得を挙げています。
有資格者が昇進しやすい理由は、資格者がいないと受注できない工事があり、企業が経営をするうえで、貴重な人材となっているからです。
とくに1級施工管理技士を持っていると、監理技術者として大規模案件の責任者をできるため、会社側も有資格者を管理職に据える傾向が強いです。
主任や課長に昇進すれば、当然、基本給・手当が上がったり、賞与・ボーナスが上がったりします。
1級施工管理技士の資格を取得して昇進すると、年収が100万円以上アップする方もいるでしょう。
施工管理技士を取得すると、毎月の給与に資格手当が加算される会社が多いです。
資格手当の金額は、所属する会社によりますが、1級施工管理技士なら月1~3万円。
2級施工管理技士なら、0.5万円~1.5万円の資格手当を受け取れる会社が多いです。
大手ゼネコンでは月5万円の資格手当がもらえるケースもあり、数十万円の年収アップにつながります。
資格手当は、残業代や成果給とは異なり、もっているだけで毎月定額で支給されるものです。
基本給の底上げにもなるので、できるだけ早いタイミングで取得するほうがよいでしょう。
施工管理技士を取得すると、主任技術者・監理技術者として、現場の責任者を担当できます。
項目 | 1級施工管理技士 | 2級施工管理技士 |
担当工事の規模 | 大規模 | 中小規模 |
|---|---|---|
監理技術者 | 可能 | 不可能 |
主任技術者 | 可能 | 可能 |
2級施工管理技士で担当できる主任技術者は、すべての工事現場で配置が義務付けられています。
また建設業法では、請負代金額が4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)の大型工事では、1級施工管理技士が担当できる専任の監理技術者の設置が義務付けられています。
そのため施工管理技士を取得すると、主任技術者・監理技術者として、現場全体を統括するポジションを任されたり、工事現場で担当できる仕事が増えたりします。
また1級施工管理技士の資格を持っていると、一部の現場では、専任技術者として複数現場を掛け持ちも可能です。
その結果、扱う仕事の規模や経験が増えるので、今後のキャリアアップにもつながるでしょう。
施工管理技士を含めた建設業界は慢性的な人手不足の状況が進む一方で、需要は年々拡大しています。
また日本建設業連合会によると、2024年には55歳以上が約37%と高齢化が進んでおり、今後10年間で、引退する人も多くなっています。
一方で若手の人数は減少しており、29歳以下の割合は約12%です。
さらに2022年以降は、離職者数が入職者数を上回っており、働く人数は年々減少しています。
逆に建設業界の需要は拡大しており、国土交通省が2025年9月30日に発表した建設工事受注動態統計調査によると、2025年8月の大手50社の受注総額は1兆4,929億円で、前年同月比で38.9%増加しています。
上記の状況のため、即戦力となる施工管理技士(とくに1級施工管理技士)は転職市場で引く手あまたの状態であり、施工管理技士の有効求人倍率は8倍を超えています。
職業分類 | 有効求人倍率 |
建築施工管理技術者 | 8.56 |
|---|---|
土木施工管理技術者 | 16.3 |
つまり1人の求職者に対して、8件以上の求人があるということです。
先ほど紹介したとおり、建設業界の人材は減少しており、需要は拡大しています。
そのため今後も転職市場から引く手あまたの状況は続き、年収のアップも期待できます。
だからこそできるだけ早めに、施工管理技士の資格を取得することをおすすめするのです。
1級施工管理技士を取得すれば、大手ゼネコンやプラント工場に転職できる可能性もあります。
建設業界に対する需要が増加しているため、大手ゼネコンでも即戦力の中途人材の採用に積極的ですが、前提の応募条件として、1級施工管理技士の資格が必要となります。
実際、大手ゼネコン5社の応募条件(建築施工管理技士)は、以下のとおりです。
会社名 | 応募条件(資格) |
|---|---|
鹿島建設 | 一級国家資格(一級建築士,1級建築施工管理技士)もしくは同等以上の資格 |
大林組 | 一級建築士または1級建築施工管理技士(1級建築施工管理技士補の場合は要相談) |
大成建設 | 一級建築士または1級建築施工管理技士若しくは、同等以上の資格 |
竹中工務店 | 一級建築士または1級建築施工管理技士 |
清水建設 | 1級建築施工管理技士または一級建築士 |
※スーパーゼネコン5社の募集要件(中途採用)を参照
上記のとおり、1級施工管理技士の資格は、スーパーゼネコンに転職するための切符となります。
大手ゼネコンに転職できれば、年収1,000万円を超える可能性も十分ありますし、就業時間や福利厚生の大幅な改善も見込めるでしょう。
大手企業に転職する機会を得るためにも、早めに施工管理技士の資格を取得してください。
なお施工管理技士が転職するなら、プレックスジョブの利用をおすすめします。なぜならプレックスジョブは、書類選考の通過率を高めるために書類添削・書類作成の代行をしていたり、面接の通過率を高めるための面接対策(聞かれやすい質問や回答例の共有)をしたりして、転職の成功確率を最大限高めるサポートをしているからです。
プレックスジョブが施工管理の方にしているサポート内容については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:
施工管理の転職でプレックスジョブが選ばれている5つの理由
最後に施工管理技士の資格に合格するコツを3つ解説します。
事前知識の有無によりますが、1級施工管理技士の取得には最大400時間の学習が必要です。
また2級施工管理技士を取得するためには、100時間~300時間の勉強時間が必要となります。
施工管理技士として働いている方は、まずは勉強時間を捻出することから始めましょう。
なお会社によっては、資格取得支援のために残業時間や休日出勤を考慮してくれる場合もあります。
また資格取得支援制度として、学習費用や受験費用を支払ってくれる場合もあるので、資格スクールに入ったり、参考書を買ったりする前に会社の制度を確認してください。
施工管理技士の第一次検定は、マークシート形式で知識を問われる問題です。
新しい傾向の問題も出題されますが、基本的に過去に出題された論点の焼き直しのパターンが多いです。
そのため過去5年~10年分の問題集を繰り返して、問題と回答のパターンを暗記するのが早いでしょう。
なお過去問題集を繰り返すコツは、間違えた問題の解説文を丁寧に読み、反復して定着させることです。
過去問題集を完璧に解けるようになれば、第一次検定の合格はグッと近づきます。
施工管理技士の第二次検定は、実務経験をもとにした記述形式があります。
いわゆる経験記述の形式なので、単一の正解があるわけではなく、過去問題集での対策は難しいです。
実際、「自分では回答できているつもりだけど、減点されていた」という声も珍しくありません。
そこでおすすめしたいのが、すでに第二次検定に合格している人に添削してもらう方法です。
たとえば職場の先輩や上司に頼めるなら、改善点を細かく教えてもらうのが良いでしょう。
合格者は自分では気付けないポイントを教えてくれることもあるので、参考になります。
もし身近に相談できる人がいない場合は、資格学校の添削サービスを利用する方法もあります。
3万円程度で添削を受けられるサービスもあるので、どうしても必要な方は利用してください。
本記事で紹介したとおり、施工管理技士の資格は7種類あります。
1級施工管理技士の合格率を基準とした難易度ランキングは、以下のとおりです。
No | 資格の種類 | 合格率※1 |
|---|---|---|
1 | 1級建設機械施工管理技士 | 13.5% |
2 | 1級電気通信工事施工管理技士 | 16.6% |
3 | 1級造園工事施工管理技士 | 18.2% |
4 | 1級土木施工管理技士 | 18.3% |
5 | 1級建築施工管理技士 | 18.9% |
6 | 1級電気工事施工管理技士 | 28.9% |
7 | 1級管工事施工管理技士 | 39.9% |
※1. 試験実施団体の公表値(直近)をもとにストレート合格率※2を算出
※2. ストレート合格率:第一次検定の合格率×第二次検定の合格率
1級施工管理技士の合格率は、多くが20%を切っており、決して簡単ではありません。
細かな受験資格があることを踏まえると、一定の難関資格であるとも言えます。
しかし施工管理技士を取得するメリットは多く、年収が100万円以上アップしたり、大手企業に転職したりできる可能性もあります。
そのため施工管理技士としてキャリアを歩んでいきたい方は、早めに施工管理技士の資格を取得したほうがよいでしょう。
なお現在、すでに施工管理技士の資格を取得している方は、転職市場で引く手あまたの状況です。
現職より年収が100万円以上アップする可能性もあるので、ぜひ一度『年収診断』であなたの適正年収を確認してください。
施工管理技士の資格が簡単すぎるというのは、事実ではありません。
本記事で紹介しているとおり、合格率は20%を切っており、決して高くないと言えます。
また実務経験を含めた受験資格があることを考えると、一定の難関資格とも言えるでしょう。
「簡単すぎる」と言われる背景としては、第一次検定の合格率が50%を超えることもあり、一見、合格率が高いと感じることがあります。
実際には、2つの試験に通過する必要があるため、実際の合格率は20%を下回ります。
弁護士や公認会計士などと比べると難易度は低いですが、決して簡単すぎる資格ではありません。
施工管理技士で最も難易度の高いのは、1級建設機械施工管理技士です。
No | 資格の種類 | 合格率※1 |
|---|---|---|
1 | 1級建設機械施工管理技士 | 13.5% |
2 | 1級電気通信工事施工管理技士 | 16.6% |
3 | 1級造園工事施工管理技士 | 18.2% |
4 | 1級土木施工管理技士 | 18.3% |
5 | 1級建築施工管理技士 | 18.9% |
6 | 1級電気工事施工管理技士 | 28.9% |
7 | 1級管工事施工管理技士 | 39.9% |
上記のとおり、直近の試験で合格率が最も低いのは、1級建設機械施工管理技士でした。
そのため施工管理技士で最も難易度が高いのは、1級建設機械施工管理技士と言えるでしょう。
施工管理技士を取得すれば、年収が上がる可能性は高いです。
なぜなら昇進・昇格で基本給が上がったり、資格手当をもらえたりするからです。
また1級施工管理技士を取得して現場の責任者になれば、責任者手当としてさらに給料が増えます。
結果的に、年収が100万円以上アップする方もいるでしょう。
なお施工管理技士は、転職市場からの評価も高く、年収アップの転職も実現しやすいです。
つまり社内でキャリアを作る場合でも、転職でキャリアアップする場合でも、施工管理技士を取得すれば年収が上がる可能性は高いでしょう。
1級施工管理技士と2級施工管理技士では、扱う工事の規模と役割が違います。
項目 | 1級施工管理技士 | 2級施工管理技士 |
担当工事の規模 | 大規模 | 中小規模 |
|---|---|---|
監理技術者 | 可能 | 不可能 |
主任技術者 | 可能 | 可能 |
1級施工管理技士は、大規模工事で監理技術者を担当できますが、2級施工管理技士が担当できるのは、中小規模の工事の主任技術者までです。
たとえばハウスメーカーの施工管理であれば、2級施工管理技士でも十分対応できる工事が多いです。
ただし大規模な公共工事やオフィスビルなどの施工管理には、1級施工管理技士が必須となります。
結論、未経験でいきなり1級の施工管理技士を取得することはできません。
なぜなら1級施工管理技士の第二次検定では、受験資格として、実務経験が必須だからです。
ただし1級施工管理技士の第一次検定は、満19歳以上であれば、誰でも受験可能です。
いきなり1級施工管理技士にチャレンジしたい方は、まず第一次検定を受けて、実務経験を積んだ後に、第二次検定の合格を目指しましょう。
他の資格と比べると、難易度は『中の中~中の上』と言えるでしょう。
実際、多くの資格比較サイトでは、1級施工管理技士の偏差値は52~55で、2級施工管理技士の偏差値は48~50となっています。
偏差値の平均は50なので、施工管理技士の難易度は平均よりやや上と考えて問題ありません。
それぞれの事前知識の有無によって変わりますが、1級施工管理技士の取得には、最大400時間。
2級施工管理技士を取得するためには、100時間~300時間の勉強時間が必要と言われています。
つまり1級施工管理技士に合格するには、1日1時間の学習を1年すれば良い計算です。
また経験や知識が豊富な人であれば、3ヶ月以内で合格できる方もいるでしょう。
施工管理技士はやめとけと言われる理由は、3K(きつい・汚い・危険)のイメージが強いからです。
ただし近年では、働き方改革やIT化・DX化の影響で、施工管理技士の働きやすさは改善されています。
また施工管理技士は比較的年収も高い職業のため、イメージ以上に働きやすく、収入が高いと言えます。
「施工管理はやめとけ」と言われる理由は、以下の記事で詳しく紹介しているので参考にしてください。
関連記事:なぜ施工管理はやめとけと言われるのか?

プレックスジョブマガジンは、累計100万人以上の方にご登録いただいている求人サイト「プレックスジョブ」が運営するメディアです。 7年以上にわたりドライバー・製造職・施工管理といったエッセンシャルワーカーの転職支援に携わっており、各業界で働く方・これから目指す方のために、役立つ情報を発信しています。 仕事や転職に関する記事を通じて、キャリア支援をしています。


1級電気工事施工管理技士の難易度を徹底解説。令和7年度の合格率は28.9%(第一次検定:41.5%、第二次検定:69.6%)、偏差値54相当。2級との違い、試験概要、独学での合格方法まで解説
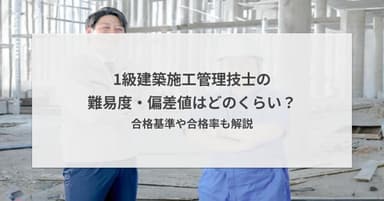
1級建築施工管理技士の難易度を徹底解説。令和6年度の合格率は14.8%、偏差値55相当。資格の試験内容、必要な勉強時間、独学での合格方法まで、プロの専門家が解説します。
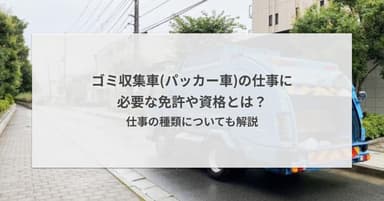
ゴミ収集車に必要な免許は、準中型免許もしくは中型免許です。学歴・経験不問の求人も多く、異業種からの転職ハードルも低い職業です。また、民間事業者のゴミ収集員なら普通免許から応募できる場合もあり、資格支援制度で働きながら資格取得を目指すこともできます。本記事ではゴミ収集車に必要な免許・資格について解説します。
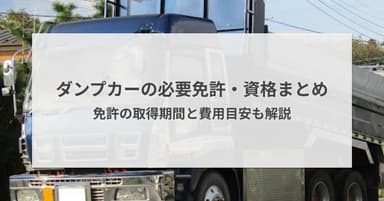
ダンプカー運転手に必要な免許を一覧でわかりやすく解説。あわせて取得しておきたい資格3選も紹介します。この記事を読めば、これからダンプカー運転手を目指す方が何から始めるべきか分かります。
.jpg&w=384&q=75)
牽引免許は難しい資格ではなく、警視庁のデータでは合格率81%です。本記事では、牽引免許の費用や期間、教習所・一発試験で取得する違いまでわかりやすくまとめています。牽引免許の取得を検討している方は必見です。
お知らせ
2025/09/06
一般社団法人キャリア協会様に「プレックスジョブ」が掲載されました
お知らせ
2025/08/05
ひとキャリ様に「プレックスジョブ」が掲載されました
お知らせ
2025/05/20
【エッセンシャルワーカー転職市場のリアル調査第3弾】利用者満足度97%以上のプレックスジョブから見る、求職者が"転職サービスに求めること"
お知らせ
2025/05/15
【エッセンシャルワーカー転職市場のリアル調査第2弾】施工管理・電気設備管理職の転職理由1位は"キャリアアップ・スキルアップ" 40~50代に広がる再挑戦の動き
お知らせ
2025/05/13
【エッセンシャルワーカー転職市場のリアル調査第1弾】「今すぐ変えたい」から始まる転職 ドライバーの"リアルな職場選びの基準"
お知らせ
2024/10/31
日本最大級の運送|建設|技術職の求人サイト「プレックスジョブ」 累計登録者数が100万人を突破 〜企業からの直接スカウトや専属アドバイザーのサポートで求職者を支援、利用者様の満足度は95%以上〜
Q. 「プレックスジョブ」の掲載求人には、どのような種類のお仕事がありますか?
物流・建設業界を中心にドライバー(貨物・旅客)や運行管理者、施工管理技士や職人といった様々な職種の求人を掲載しております。中でもドライバーの求人は20,000件を超えており、大型トラックの運転手から軽貨物の配送、タクシー・バスの運転手など、様々な求人を掲載しています。
Q. 未経験でも応募可能ですか?
応募する職種の就業経験がない方でも、積極的に募集している求人も多数ございますので、未経験の方も応募は可能です。一方で、応募条件を経験者のみに限定している場合もございますので、条件をよく確認してから、応募しましょう。
必要資格を持っていない場合でも、入社後に、必要な免許を取得するチャレンジを応援している企業もあります。免許取得支援制度は、会社側が運転免許の取得に掛かる費用を全額もしくは一部を補助してくれる制度です。制度を利用する際には、規定もありますので、事前に確認しておきましょう。
Q. 費用はかかりますか?
登録から転職決定まで費用は一切発生いたしません。どんな求人があるのか知りたい、話だけ聞いてみたいといった方でも問題ございませんので、お気軽にご登録ください。