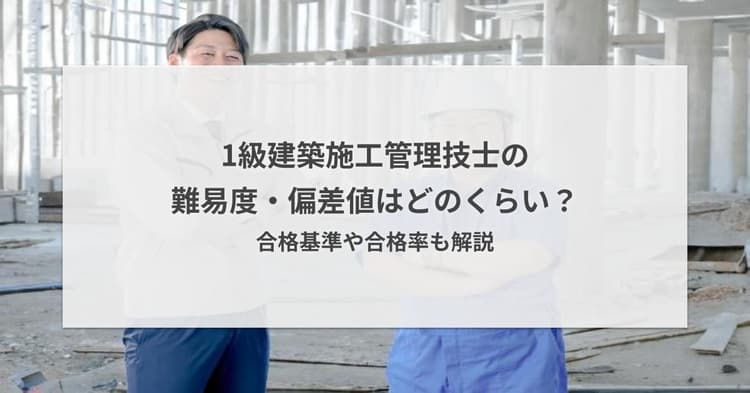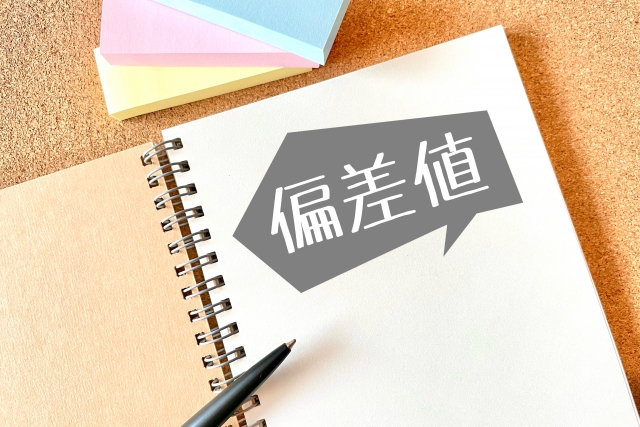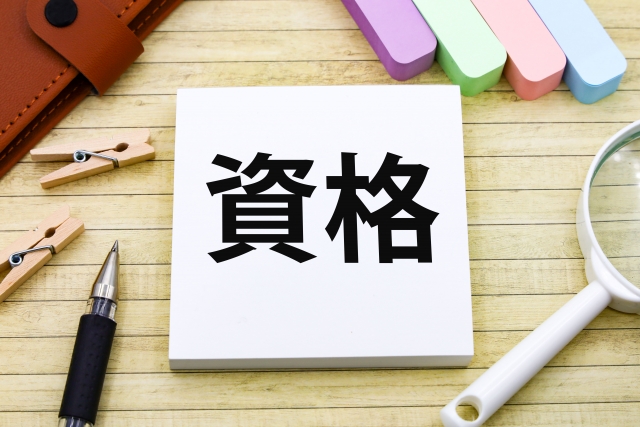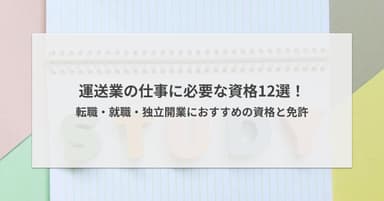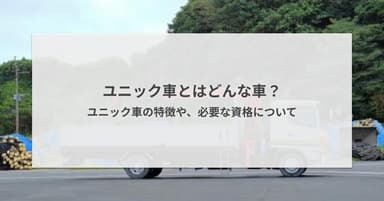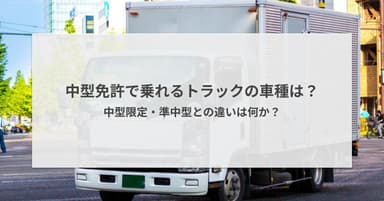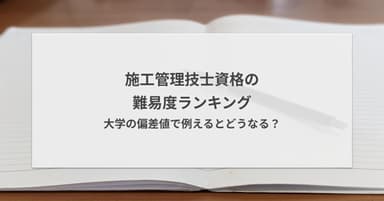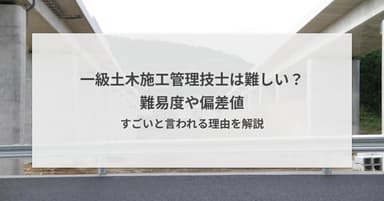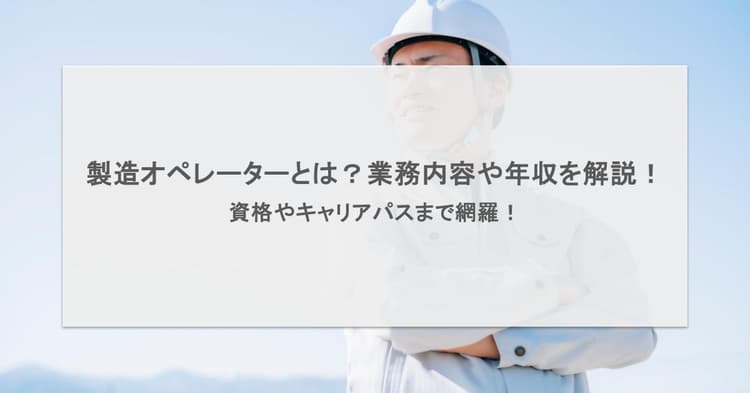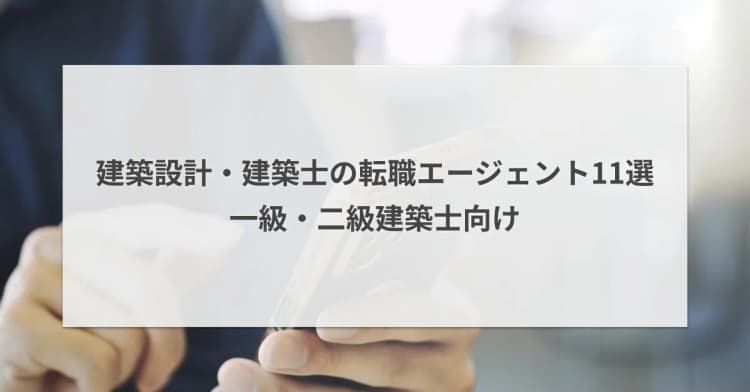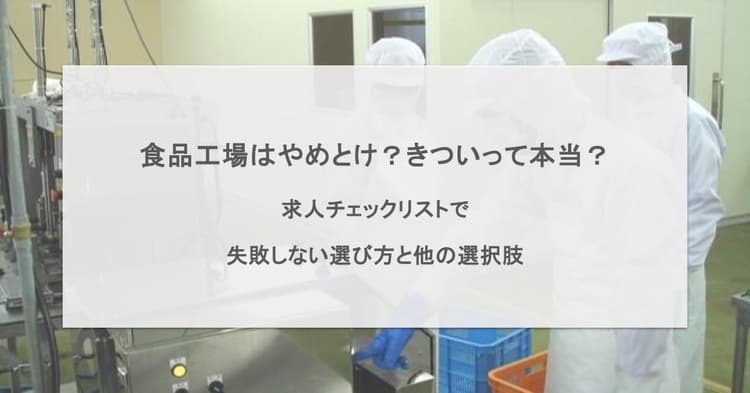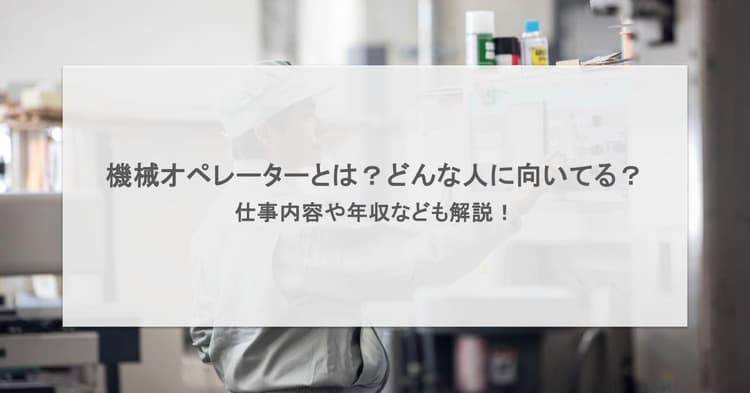1級建築施工管理技士の難易度・偏差値
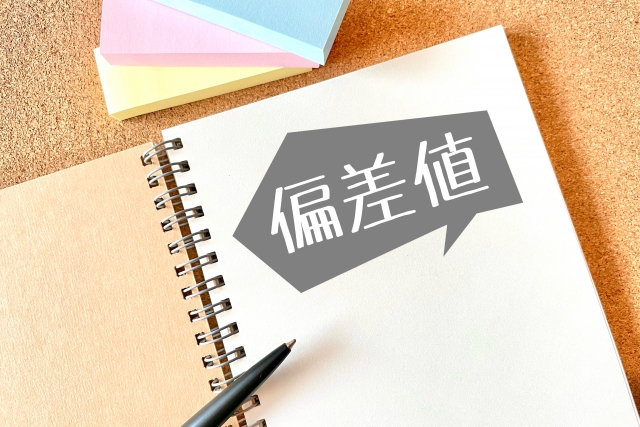
1級建築施工管理技士の難易度は高めで、偏差値でいうと”55”です。
2級建築施工管理技士の偏差値が”50”なので、1級建築施工管理技士の難易度は高めとわかります。
とはいえ「1級建築施工管理技士ってどのくらい難しいの?」と疑問を持つ方もいるでしょう。
ここからは、1級建築施工管理技士の合格率の推移や合格基準を解説します。
1級建築施工管理技士の合格率と合格者数の推移
1級建築施工管理技士は、1次試験(マークシート)と2次試験(マークシート+記述形式)の2つの試験に通過する必要があります。
まず1次試験について合格者数と合格率の推移は、以下のとおりです。
1次試験 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|
受験者数 | 41,812人 | 37,651人 | 24,078人 | 27,253人 | 22,277人 |
|---|
合格者数 | 20,294人 | 13,624人 | 10,017人 | 12,755人 | 8,025人 |
|---|
合格率 | 48.5% | 36.2% | 41.6% | 46.8% | 36.0% |
|---|
つづいて2次試験の合格者数と合格率の推移は、以下のとおりです。
2次試験 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|
受験者数 | 18,159人 | 14,816人 | 14,391人 | 13,010人 | 12,813人 |
|---|
合格者数 | 6,042人 | 6,042人 | 6,544人 | 5,878人 | 6,708人 |
|---|
合格率 | 39.0% | 40.8% | 45.5% | 45.2% | 52.4% |
|---|
各試験の合格率は40%と高めに見えますが、2つの試験の最終的な合格率でみると、合格率が20%以下の難関資格となります。
たとえば令和7年度の試験の場合、最終的な合格率は約19%です。
※1次試験の合格率:48.5%、2次試験の合格率:39.0%
とくに2次試験の難易度は高く、受験者は1次試験の合格者のみに限定されているにもかかわらず、合格率は50%を下回る事が多いです。
さらに2次試験には、去年や一昨年の1次試験に通過し、1年勉強して挑戦する”再受験組”も存在します。
そのため同じ年に1次試験と2次試験と突破するストレート合格の合格率は、20%よりも低くなるでしょう。
1級建築施工管理技士の資格難易度が高い理由
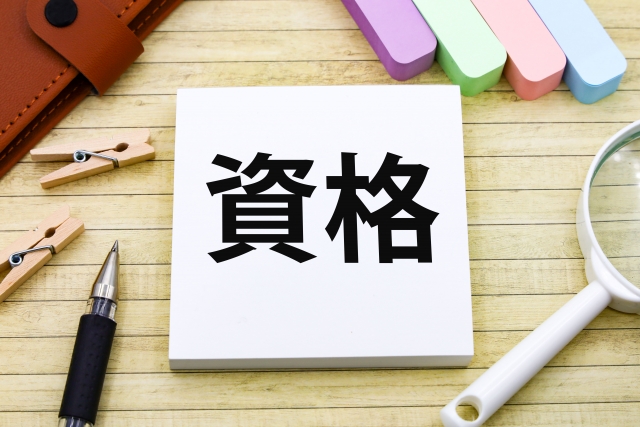
ここまで紹介したとおり、1級建築施工管理技士の資格難易度は比較的高いです。
そして1級建築施工管理技士の資格難易度が高い理由は、以下の3つがあります。
- 1級建築施工管理技士は試験範囲が広くて専門性が高い
- 1級建築施工管理技士は2次試験(旧:実地試験)の記述が難しい
- 1級建築施工管理技士は受験資格(実務経験要件)のハードルが高い
1級建築施工管理技士は試験範囲が広くて専門性が高い
1級建築施工管理技士の難易度が高い最大の理由は、試験範囲が広くて専門性が高いからです。
1次試験(1級建築施工管理技士)の試験範囲は、以下になります。
■1次試験. 検定科目:建設学等(マークシート)
1. 建築一式工事の施工の管理を的確に行うために必要な建築学、土木工事、電気通信高額及び機械工学に関する一般的な知識を有すること
2. 建築一式工事の施工の管理を的確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること
■1次試験. 検定科目:施工管理法(マークシート)
1. 監理技術者補佐として、建築一式工事の施工の管理を的確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理投稿時の施工の管理方法に関する知識を有すること
2. 監理技術者補佐として、建築一式工事の施工の管理を的確に行うために必要な応用能力を有すること
■1次試験. 検定科目:法規(マークシート)
建設工事の施工の管理を的確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること
■2次試験. 検定科目:施工管理法(マークシート)
1. 監理技術者として、建築一式工事の施工の管理を的確に行うために必要な知識を有すること
■2次試験. 検定科目:施工管理法(記述)
2. 監理技術者として、建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる応用能力を有すること
3. 監理技術者として、設計図書に基づいて、工事現場における施工管理を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる応用能力を有すること
上記のとおり、1級建築施工管理技士で問われる内容は幅広いです。
さらに2次試験では、記述式で応用能力を問われるので、難易度が高くなってしまいます。
1級建築施工管理技士は2次試験(旧:実地試験)の記述が難しい
先ほど紹介したとおり、1級建築施工管理技士の2次試験は記述式です。
実際に令和5年度の試験問題は、以下のとおりです。
問題:建築工事における次の1.から3.の仮設物の設置を計画するに当たり、留意すべき事項及び検討すべき事項を、それぞれ2つ具体的に記述しなさい。ただし解答はそれぞれ異なる内容の記述とし、申請手続、届出及び運用管理に関する記述は除くものとする。また使用資機材に不良品はないものとする。
1. くさび緊結式足場
2. 建設用リフト
3. 場内仮設道路
2次試験では、上記のような記述問題が合計4問出題されます。
また1級建築施工管理技士の記述問題は、建築施工管理に関する基礎的な知識だけではなく、監理技術者に必要な応用能力が問われます。
上記の問題を含めて、60%以上の得点が必要なため、1級建築施工管理技士の難易度は高いのです。
1級建築施工管理技士は受験資格(実務経験要件)のハードルが高い
1級建築施工管理技士の受験資格(実務経験要件)は厳しく、施工管理の実務経験が必要です。
2024年の制度改正で少し緩和されましたが、依然として受験ハードルは高めです。
1級建築施工管理技士の1次試験の受験資格は年齢のみです。
ただし2次試験の受験資格は、実務経験が5年以上必要だったり、1次試験の合格や2級建築施工管理技士の資格が必須だったりします。
そのため1級建築施工管理技士の受験資格すら得られない施工管理技士もいます。
だからこそ1級建築施工管理技士の難易度が高いと言われるのです。
1級建築施工管理技士に合格する方法

資格を取得する難易度の高い1級建築施工管理技士ですが、毎年5,000人以上の合格者がいます。
最後に、1級建築施工管理技士に合格する方法を3つご紹介します。
- 1級建築施工管理技士の試験内容を確認する
- 1級建築施工管理技士に必要な知識を勉強する
- 1級建築施工管理技士の模擬面接を受ける
1級建築施工管理技士の試験内容を確認する
1級建築施工管理技士の資格取得を目指すなら、最初に試験内容を確認してください。
前提として、1級建築施工管理技士の試験範囲は幅広いです。
そのため試験に必要のない部分を勉強すると、必要な部分に時間を使えず、合格できない可能性もでてきます。
だからこそ1級建築施工管理技士を受験するなら、はじめに試験内容の確認が必要になるのです。
1級建築施工管理技士に必要な知識を勉強する
1級建築施工管理技士の試験範囲を確認したあとは、合格に必要な知識を勉強していきます。
なお1級建築施工管理技士の勉強をする場合、通信講座で学ぶか、独学で学ぶかを選ぶ必要があります。
1級建築施工管理技士を通信講座で学ぶメリットは、合格までの期間が短くなる可能性があることです。
ただし通信講座の場合、1次試験と2次試験の合計で50万円以上の費用がかかるデメリットもあります。
独学で1級建築施工管理技士を目指す方は、参考書・過去問題集やYouTubeの動画での勉強になります。
勉強のコストは1万円以下にできるものの、1級建築施工管理技士に合格するまでの期間が長い可能性があるデメリットもあります。
1級建築施工管理技士の模擬試験を受ける
1級建築施工管理技士に必要な知識を勉強した方は、TACや日建学院などで、模擬試験を受けましょう。
模擬試験では、実際の試験と同じような環境で、本試験同様の問題を解くことができます。
複数回の模擬試験を受ければ、試験問題の傾向を把握することができますし、本番の緊張も減らせます。
1級建築施工管理技士の試験は、年に1回しか実施していないので、落ちると来年まで時間が空くデメリットもあるのです。
上記のようなリスクを避けるためにも、模擬試験を受けて、本番への慣れをしておくのがおすすめです。
1級建築施工管理技士を取得するメリット3選

1級建築施工管理技士は資格の取得難易度が高いものの、取得するメリットもあります。
1級建築施工管理技士を取得するメリットは、以下の3つです。
- 1級建築施工管理技士の取得で年収をアップできる
- 1級建築施工管理技士なら定年後も働ける
- 1級建築施工管理技士の取得でキャリアの幅が広がる
1級建築施工管理技士の取得で年収をアップできる
1級建築施工管理技士を取得すれば、転職や昇進で有利になり、年収が100万円上がるケースもあります。
一番わかりやすい昇給は資格手当で、毎月3万円以上の資格手当をもらえる会社もあります。
そして1級建築施工管理技士が転職や昇進で有利になる理由は、監理技術者として、大規模な工事の現場責任者になれるからです。
監理技術者は、大規模な工事(元請金額が5,000万円以上)に必須の資格になります。
そして工事の規模が大きくなるほど、会社の利益も増える傾向にあるので、会社としては、多額の給料を支払っても雇うメリットがあります。
だからこそ1級建築施工管理技士の資格を持っていれば、年収が100万円以上上がることもあるのです。
関連記事:1級建築施工管理技士の平均年収・給料はいくら?資格手当・年代別年収・1,000万円狙う方法も解説
1級建築施工管理技士なら定年後も働ける
1級建築施工管理技士の資格を持っていれば、60代や70代などの定年後でも働けます。
なぜなら1級建築施工管理技士は『専任技術者』や『管理技術者』として、自分の手を動かさずに、現場を管理したり、若手に作業を教えたりすることができるからです。
実際にプレックスジョブを利用した方には、70代(施工管理の経験者)でも転職に成功した方もいます。
1級建築施工管理技士の資格を持っていれば、60代以降も安定した収入を得られる可能性が高まります。
1級建築施工管理技士の取得でキャリアの幅が広がる
1級建築施工管理技士を取得すれば、キャリアの幅が広がることもメリットです。
たとえば1級建築施工管理技士の資格を取得すれば、現職で年収を上げるだけではなく、大手ゼネコンや大手不動産会社へのキャリアアップ転職も可能になります。
実際にスーパーゼネコン5社の募集要項を見ると、1級建築施工管理技士が求められているとわかります。
会社名 | 応募条件(資格) |
|---|
鹿島建設 | 一級国家資格(一級建築士,1級建築施工管理技士)もしくは同等以上の資格 |
|---|
大林組 | 一級建築士または1級建築施工管理技士
(1級建築施工管理技士補の場合は要相談) |
|---|
大成建設 | 一級建築士または1級建築施工管理技士若しくは、同等以上の資格 |
|---|
竹中工務店 | 一級建築士または1級建築施工管理技士 |
|---|
清水建設 | 1級建築施工管理技士または一級建築士 |
|---|
表のとおり、1級建築施工管理技士はスーパーゼネコンに応募する条件になりますし、中規模から小規模の施工管理会社なら即戦力として幹部クラスでの転職の可能性すらあります。
小規模から中規模で働いている方でも、スーパーゼネコンに入るチャンスが得られたり、幹部候補としてキャリアアップできたりすることも、1級建築施工管理技士を取得するメリットと言えるでしょう。
1級建築施工管理技士を取得するより早く年収を上げる方法

「1級建築施工管理技士の資格を取るのは難しそう。でも年収は上げたい」
上記のように考えている方は、1級建築施工管理技士を取得するよりも、転職をする方が、早く年収を上げられます。
なぜなら1級建築施工管理技士の資格取得には、長いと5年以上の時間がかかる一方で、転職は最短3ヶ月ほどで年収をアップさせることができるからです。
2級建築施工管理技士でも、転職をすることで、年収を100万円以上UPさせられる可能性があります。
実際にプレックスジョブで転職した2級建築施工管理技士の方(50代男性)には、年収を650万円から850万円以上にUPできた事例もあります。
関連記事:
施工管理の転職でプレックスジョブが選ばれている5つの理由
この方は転職後に1級建築施工管理技士を取得する予定とのことで、転職して年収を上げた後で、1級建築施工管理技士を取るという方法でキャリアアップを実現しています。
この方のように、先に転職して後から1級建築施工管理技士を取ることもできるので、「早く給料を上げたい」と考えているなら、1級建築施工管理技士を取得する前に転職するのも一つの手です。
プレックスジョブでは、実際のオファー金額も提示しているので、自分が転職した後に受けられる年収を知りたい方は試してみてください。
\ 簡単30秒登録 /
> 建築施工管理技士向け高年収求人をみてみる <
まとめ
本記事では、1級建築施工管理技士の難易度について、以下の内容を紹介しました。
- 1級建築施工管理技士の難易度と偏差値
- 1級建築施工管理技士の合格率と推移
- 1級建築施工管理技士と難易度が高い理由
本記事で紹介したとおり、1級建築施工管理技士の難易度は高めで、令和5年度の合格率は14.76%と低い数字でした。
また1級建築施工管理技士の試験は、年に1回しか実施されず、試験に落ちると来年まで資格を取得できない点には注意が必要です。
1級建築施工管理技士の難易度が高い理由は、以下の3つがあります。
- 1級建築施工管理技士は試験範囲が広くて専門性が高い
- 1級建築施工管理技士は2次試験(旧:実地試験)の記述が難しい
- 1級建築施工管理技士は受験資格(実務経験要件)のハードルが高い
ただし1級建築施工管理技士を取得することで、年収100万円上がる可能性があるなど、大きなメリットがあることもたしかです。
「1級建築施工管理技士を取得するか迷っている...」という施工管理技士は、取っておいて損はない資格なので、取得を目指すことをおすすめします。
「1級建築施工管理技士の試験の勉強は面倒だけど、現状より年収を上げたい」という方は、リアルな年収のわかるプレックスジョブで年収診断をしてみてくださいね。
→簡単30秒|年収診断で市場価値を調べてみる
1級建築施工管理技士の難易度・偏差値に関するよくある質問

最後に1級建築施工管理技士の難易度・偏差値に関するよくある質問に回答します。
1級建築施工管理技士の受験資格と合格基準
前提として、1級建築施工管理技士の試験は、全員が受けられるわけではありません。
1級建築施工管理技士の受験資格は、以下のとおりです。
試験 | 必要条件 |
|---|
1次試験 | 試験実施年度に満19歳以上となる者 (令和7年度に申請する場合、生年月日が平成19年4月1日以前) |
|---|
2次試験
※1級第一次検定合格者 | ・1級建築第一次検定合格後、実務経験5年以上 ・1級建築第一次検定合格後、特定実務経験 (※1) 1年以上を含む実務経験3年以上 ・1級建築第一次検定合格後、監理技術者補佐 (※2) としての実務経験1年以上 |
|---|
2次試験
※1級第一次検定、および2級第二次検定合格者 | ・2級建築第二次検定合格後 (※3)、実務経験5年以上 ・2級建築第二次検定合格後 (※3)、特定実務経験 (※1) 1年以上を含む実務経験3年以上 |
|---|
2次試験
※1級第一次検定受検予定、および2級第二次検定合格者 | ・2級建築第二次検定合格後 (※3)、実務経験5年以上 ・2級建築第二次検定合格後 (※3)、特定実務経験 (※1) 1年以上を含む実務経験3年以上 |
|---|
2次試験
※一級建築士試験合格者 | ・一級建築士試験合格後、実務経験5年以上 ・一級建築士試験合格後、特定実務経験 (※1) 1年以上を含む実務経験3年以上 |
|---|
※1 建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円(建築一式工事については7,000万円)以上の建設工事であって、監理技術者・主任技術者(いずれも実務経験対象となる建設工事の種類に対応した監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者若しくは主任技術者として行った施工管理の実務経験を指します。
※2 1級建築施工管理技士補の資格を有し、かつ当該工事における主任技術者要件を充足する者が、監理技術者の専任が必要となる工事において、監理技術者の職務を専任として補佐した経験をいいます。単なる監理技術者の補助経験は対象になりません。
※3 旧2級施工管理技術検定実地試験合格者を含み、種別(建築・躯体・仕上げ)を問いません。
参照:令和7年度 1級 建築施工管理技術検定のご案内 | 一般財団法人建設業振興基金
1次試験の必要条件は年齢のみですが、2次試験を受験するには、1年以上の実務経験が求められます。
なお監理技術者補佐として1年以上の経験を積むルートは、1級建築施工管理技士補の資格取得が前提となるため、現実的には2級建築施工管理技士取得後の実務経験(最短3年)が一般的です。
上記の受験資格を持った上で、1級建築施工管理技士の合格基準は、各試験の得点が60%以上です。
試験 | 合格基準 |
|---|
1次試験
(全体) | 得点が60% |
|---|
1次試験
(施工管理法※応用能力) | 得点が60% |
|---|
2次試験 | 得点が60% |
|---|
参照:令和7年度技術検定の合格基準について | 国土交通省
ここで気をつけたいポイントは、1次試験の施工管理法の項目での得点が最低でも60%必要なことです。
全体で60%を超えていても、施工管理法の得点が60%未満だと不合格なので注意が必要になります。
1級建築施工管理技士と2級建築施工管理技士との難易度比較
1級建築施工管理技士の試験は、2級建築施工管理技士の試験と比べて、難易度がグッと高くなります。
1級建築施工管理技士と2級建築施工管理技士の合格率は、それぞれ以下のとおりです。
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|
1級建築施工管理技士の合格率 | ー | 14.76% | 18.92% | 21.15% | 18.86% |
|---|
2級建築施工管理技士の合格率 | ー | 19.61% | 12.06% | 26.92% | 20.05% |
|---|
1級建築施工管理技士と2級建築施工管理技士の合格率は、2級建築施工管理技士が少し高い状態です。
ただし1級建築施工管理技士の受験者は、2級建築施工管理技士や一級建築士の資格保有者や、1級建築施工管理技士の1次試験合格後に5年以上の実務経験がある人に限定されています。
なお1級建築施工管理技士と2級建築施工管理技士では、合格率以外に、以下のような差があります。
項目 | 1級建築
施工管理技士 | 2級建築
施工管理技士 |
|---|
役職 | 監理技術者 | 主任技術者 |
|---|
対象工事 | あらゆる規模の工事 | 小規模な工事 ※請負金額5,000万円未満(建築一式工事では8,000万円未満) |
|---|
試験内容 | 高度な構造計算や大規模工事の総合管理、複雑な法令の解釈 | 基礎的・一般的な知識 |
|---|
学習時間の目安 | 400~600時間 | 200~300時間 |
|---|
1級建築施工管理技士は、あらゆる規模の工事で監理技術者になれる分、試験内容も複雑です。
だからこそ合格率の差以上に、1級建築施工管理技士と2級建築施工管理技士の難易度に差があるのです。
1級建築施工管理技士は一級建築士・二級建築士より難易度が高い?
1級建築施工管理技士は、一級建築士・二級建築士よりも難易度が低いと考えられます。
資格 | 合格率
(令和6年度) | 偏差値 |
|---|
1級建築
施工管理技士 | 14.76% | 55 |
|---|
一級建築士 | 7.64% | 66 |
|---|
二級建築士 | 21.8% | 56 |
|---|
表のとおり、二級建築士は1級建築施工管理技士より偏差値がわずかに高く、一級建築士の偏差値は大幅に高くなっています。
ただし1級建築施工管理技士は”施工管理”の資格で、一級建築士や二級建築士は”設計”です。
それぞれの業務内容が異なるため、単純な難易度の比較は難しいことには注意しておくべきでしょう。
二つの資格で悩んでいる方は、自分の理想的なキャリアを考えて、自分にあう資格を目指してください。
1級建築施工管理技士は独学でも合格できる?
1級建築施工管理技士は独学でも合格できる可能性はあります。
独学で勉強する場合は、参考書や過去問題集。
YouTubeなどの動画を使って勉強しましょう。
ただし独学は、合格までの時間が長くなる可能性があるというデメリットも注意が必要です。
最短で1級建築施工管理技士の資格を取得したい方は、通信講座の受講も検討してください。
1級建築施工管理技士を取得したら年収が上がる?
1級建築施工管理技士を取得すれば、年収は上がる可能性が高いです。
とはいえ1級建築施工管理技士を取得しただけで、年収が上がるわけではありません。
1級建築施工管理技士を取得した結果、本業で大規模な工事を担当したり、転職でキャリアアップしたりすることで、年収を上げられます。
関連記事:1級建築施工管理技士の平均年収・給料はいくら?資格手当・年代別年収・1,000万円狙う方法も解説
1級建築施工管理技士を取得したら転職しやすい?
1級建築施工管理技士を取得すれば、転職しやすくなります。
実際にスーパーゼネコンの中途採用における応募条件を確認しても、1級建築施工管理技士を持っていれば応募できます。
会社名 | 応募条件(資格) |
|---|
鹿島建設 | 一級国家資格(一級建築士,1級建築施工管理技士)もしくは同等以上の資格 |
|---|
大林組 | 一級建築士または1級建築施工管理技士
(1級建築施工管理技士補の場合は要相談) |
|---|
大成建設 | 一級建築士または1級建築施工管理技士若しくは、同等以上の資格 |
|---|
竹中工務店 | 一級建築士または1級建築施工管理技士 |
|---|
清水建設 | 1級建築施工管理技士または一級建築士 |
|---|
表のとおり、1級建築施工管理技士はスーパーゼネコンの応募条件ですし、中堅ゼネコンならマネジメントクラスで採用されるチャンスも十分あります。
また今後、インフラの老朽化や都市の再開発など、大規模な建設工事が多くなる見込みがあるため、1級建築施工管理技士の需要は増加傾向にあり、将来性も高いです。
そのため1級建築施工管理技士を取得すれば、転職しやすくなると言えるのです。
1級建築施工管理技士の資格を取った後はどうしたらいい?
1級建築施工管理技士の資格を取った後は、実務経験を積んで、年収の高い企業に転職する。
実務経験のある1級建築施工管理技士の資格保有者は、転職市場では引く手あまたなので、現職より高い年収での転職も可能でしょう。
また施工管理に役立つ別の資格取得を目指すのもおすすめです。
たとえば一級土木施工管理技士の資格を取得して、ダブルライセンスになれば、扱える仕事の幅は増えますし、より良い条件での転職も可能になります。
関連記事:施工管理技士資格の難易度ランキング